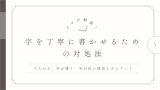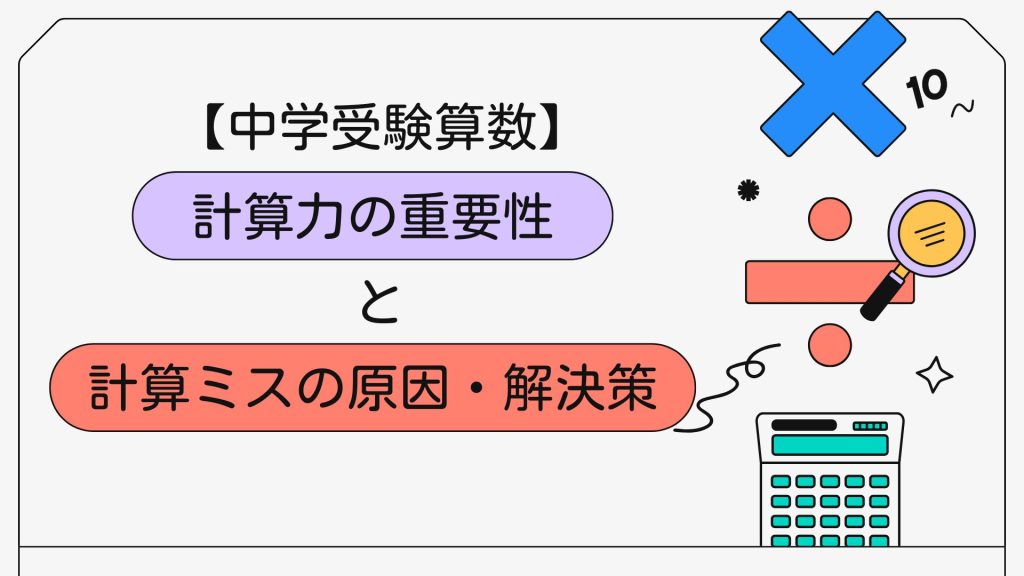
こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。

うちの子、計算ミスが多すぎる…
どうやったら計算まちがいを減らせるの?
そのようにお悩みのお母様・お父様も多いのではないでしょうか?
今回の記事では…
- 計算力の重要性
- なぜ計算ミスをするのか
- 計算ミスの解決策
がわかります。
計算力は、算数の土台です。
計算のまちがいを減らし、算数を味方につけましょう!

元塾講師・現プロ家庭教師が、のべ1000人以上を担当してきたノウハウをお伝えします
【中学受験】算数ではなぜ計算力が必要なの?
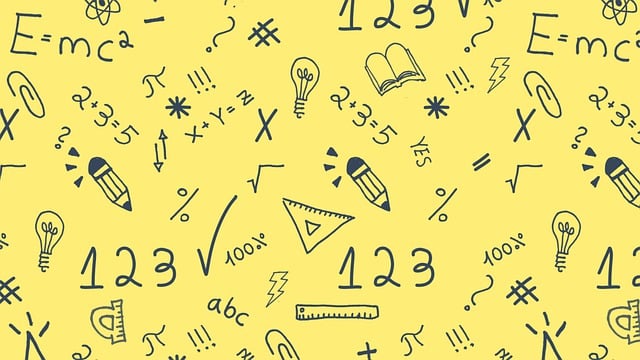
まず計算の力が必要な理由からチェックしておきましょう。
「計算力が重要なのは当たり前!」というかたは、読み飛ばしてくださいね。
中学受験算数で計算力が大切なのは…
- 計算でまちがったら水の泡
- 脳の容量を思考に使える
からです。
もう少し掘り下げて見ておきましょう。
計算でまちがったら水の泡
計算問題はもちろん、どんな問題にも計算が関わってきます。
文章題の解き方がわかっても、図形の補助線が思いついても、計算をまちがってしまうとすべてが水の泡になってしまいます。
部分点は(基本的に)ありませんから、計算ミスは0点になってしまいます。

誰もが経験することやんな…
入試のときには、わずか数点で合否が分かれます。
もしかしたら計算まちがいの1問(たとえば4点)が、勝負の分かれ目になるということはあり得ますね。
脳の容量を思考に使える
中学受験の算数の難しさであり、醍醐味は「考えること」にあります。
思考力を伸ばすために、植木算やつるかめ算などの特殊算(古典算)や、複雑な図形問題を学習します。
ただ、計算力がおぼつかないと、肝心の「考えること」に力を割くことができません。

類題を使ったパターン演習は大切ですが、その目的は「思考力アップ」だと私は思っています
脳の作業スペースには限りがあります。
いわゆる「ワーキングメモリー」ってやつですね。
問題のレベルが上がってくると、いくつか思考の手順を踏まなければ答えにたどりつけません。
計算で脳の作業スペースがいっぱいになってしまったら、考える余地がなくなってしまいます。
その結果、計算で必死になっているうちに、「あれ?何のために計算していたんだっけ?」ということが起こり得ますね…

私はそれを「計算迷子」と呼んでいます
計算はあくまで「道具」です。
道具の使い方で手間取っていては、作品を作るのに時間がかかってしまいますし、うまく作れません。
同じように、計算に手間取っていては、問題を解くのに時間がかかってしまいますし、なかなか正解までたどり着けないでしょう。
計算で脳のメモリを使わず、思考に脳の力を使いたいものです。
※中学受験合格へのロードマップはこちらの記事をどうぞ↓
【原因】どうして計算ミスをするの?

では、どうして計算ミスをしてしまうのでしょうか?
計算でまちがってしまう原因はいくつかあります。
- 苦手な計算がある
- ひっ算を使わず暗算でまちがってしまう
- 途中式を飛ばす
- 字が雑で自分でだまされる
- ひっ算が斜めになってケタをまちがう
- 検算(確かめ)をしていない
- 点数への執着がない
の7つがよくある原因です。
また、これらのいくつかがからみあって計算ミスを生むこともあります。
掘り下げて見ていきましょう。
苦手な計算がある
よくミスしてしまう原因は、苦手な計算があるのかもしれません。
- 通分が苦手(公倍数を見つけるのが遅い)
- 約分が苦手(公約数を見つけるのが遅い)
- 逆算(□算)の引き算・わり算がよくまちがう
というように、苦手なポイントは人それぞれです。
苦手な計算がある場合、「見直しをしよう」とか「ミスに気を付けて!」とアドバイスをしても、正解することができません。
計算自体があやふやなので、見直しをしてミスに気を付けようにも、ミスに気が付けないでしょう。
よく「ケアレスミス」という言い方をしますが、本当に「ケアレス(不注意)」なのかは疑う余地があります。
もしケアレスではないなら、単に実力不足であり、計算力を鍛える必要があるでしょう。
ひっ算を使わず暗算でまちがってしまう
また、本来ならひっ算で計算すべきところで、暗算して計算まちがいにつながることも多いですね。
テストで時間に追われているときや、面倒くさがりな子が、やってしまいがちです。
途中式を飛ばす
ひっ算を使わないのと同じくらいミスの発生源になっているのが、「途中式飛ばし」です。
一度にいくつかのことを同時に処理しようとするので、ミスが起こるのは当然です。
さきほどの脳の作業台(ワーキングメモリ)が、いっぱいいっぱいになった状態ですね。
字が雑で自分でだまされる
また、字が雑な子に多いのが、自分で自分をだますパターンです。
「0」で計算し始めたはずなのに、途中で「6」に変わっている…
「1」と「7」、「7」と「9」、ひどい場合「6」と「5」、「3」と「5」の見分けがつかない子もいます。
ひっ算が斜めになってケタをまちがう
ひっ算をせっかく書いたのに、そのひっ算で間違ってしまう子もいます。
だんだんひっ算が斜めになり、ケタがずれてくることがあります。
白紙の計算用紙ならまだしも、方眼ノートでもケタがずれる子も…
検算(確かめ)をしていない
計算が合っているか確かめていない子も多いですね。
いわゆる「検算(確かめ)」です。
誰でも忘れてしまったり、ミスをしてしまったりすることはあります。

だって人間だもの
でも、時間がなかったり、面倒くさがったりして、「確かめ」をせずにミスを放置してしまいます。
また、テストの「見直し」と言いますが、本当に「見ているだけ」の子もいます。
点数への執着がない
「点数への執着がない」、これが1番のくせ者です…
「1点でも落としたくない!」、「絶対に正解したい!」という得点への執着があれば、ミスを減らすための手を打つはずです。
でも、点数へのこだわりがないので…
- 字をていねいに書かない
- ひっ算を書かない
- ひっ算を書いても雑
- 途中式を飛ばす
- 検算(確かめ)をしない
といった、これまで紹介してきたミスを起こしやすい行動をとってしまうわけです。
「ケアレス(不注意)」というよりも、ケア(注意)する意識が低い状態です。
計算ミスを減らす7つの方法

では、どうやったら計算ミスを減らすことができるのでしょうか?
計算ミスを減らす7つの解決策は…
- 苦手な計算を克服する
- 計算の工夫を学ぶ
- よく使う計算は覚えてしまう
- ひっ算・途中式を書く
- 式やひっ算をていねいに書く
- 確かめながら計算する
- 点数への執着を持つ
です。
1つ1つ見ていきましょう。
苦手な計算を克服する
苦手な計算テーマがある場合には、まずはそれを克服することが大切です。
さきほど例に挙げた苦手ポイントなら、
通分が苦手(公倍数を見つけるのが遅い)
→分数の基礎に戻ってトレーニングする
→公約数を見つけるトレーニングをする
というように、過去にさかのぼって復習することも必要でしょう。
中には「どこが苦手な計算なのかわからない…」という子もいます。
そういう場合には、ある程度、計算テーマ別に作られた教材で弱点をあぶり出してみるのもアリです。
私が計算トレーニングで使っているのは、こちらの市販の教材です↓
例題やテーマを見せずに、ノーヒントで解かせてみます。
そうすれば、よくまちがうテーマや苦手なポイントがはっきりしてきます。
教材の特徴や効率的な使い方は、こちらの記事をどうぞ↓
計算の工夫を学ぶ
計算をかんたんにする工夫も身につけておくと、ミスを防ぐことができます。
たとえば、分配法則を使えるようにしておけば…
37×102
=37×(100+2)
=37×100+37×2
=3700+74
=3774
というように、3桁×2桁を直接計算するよりも、かんたんな計算ですますことができます。
円周の側面積など公式を覚えておくと、便利なものがあります。
ミスが少なくて済みますし、時短にもなりますね。
ただ、中学受験算数特有の公式や裏技などは、プロに教えてもらわないと難しいものがあります。
また、ご家庭では、つまずきポイントを見つけたり、うまく解消できないこともあるはずです。
その場合には、塾の講師に相談するなど、外部の手を借りるようにしましょう。
算数に精通したプロ家庭教師を利用して、苦手にアプローチしてもらうのもおすすめです。
よく使う計算は覚えてしまう
円の面積・円周の長さの計算で、円周率3.14を山ほど使います…
ですので、「3.14×1桁の自然数」は覚えておくと便利です。
3.14 × 1 = 3.14
3.14 × 2 = 6.28
3.14 × 3 = 9.42
3.14 × 4 = 12.56
3.14 × 5 = 15.7
3.14 × 6 = 18.84
3.14 × 7 = 21.98
3.14 × 8 = 25.12
3.14 × 9 = 28.26
この3.14の段をゴロ合わせで覚えようとする子もいますが、「何度も計算しているうちに自然と覚える」のが理想です。
また、小数と分数の書き換え(0.375=3/8)や、平方数(12×12=144)なども慣れておきたい計算ですね。
こちらも塾講師や家庭教師などのプロの手を借りた方が早いでしょう。
ひっ算・途中式を書く
暗算ですまさず、ひっ算や途中式を書くことでミスを減らすことができます。
多くの子にとって、頭の中で処理するよりも、目で見た方がまちがいは少なくなります。
また、同時に複数のことを処理しようとするとミスを誘発しやすいので、途中式でステップを踏むといいでしょう。

フラッシュ暗算などができる子は別次元
もちろん時短のためには、暗算でできる計算を増やした方がいいのはまちがいありません。
そのためにも、自分の頭の中で処理できる限度を知っておくと、ムリな暗算をせずに済みます。
「この暗算は危険だな…」と思ったら、ひっ算や途中式を書くといいでしょう。
計算力がついてきたら、少しずつ暗算でできる計算を増やしていきましょう。
式やひっ算をていねいに書く
また、ひっ算や途中式をただ書くだけでなく、大きめの字でていねいに書いた方がいいいでしょう。
せっかくひっ算や途中式を書いたのに、字が小さすぎたり雑だったり、ひっ算が傾いてケタをまちがったりしたら、意味がありません。
計算するスペースも工夫したいものです。
いきなり問題用紙や計算用紙のど真ん中から書き始めるのではなく、用紙の上から順に書いていくなどです。
ルールを決めておくことで、頭の中も整理しながら計算を進めることができます。
ただ、字が雑な子に、ていねいな字を書かせるのは至難の業ですが…
「字を丁寧に書かせるための対処法」はこちらの記事をどうぞ↓
確かめながら計算する
よく「見直し」と言いますが、ただ見ているだけでなく、実際に手を動かして「計算し直す」ことは当然ですね。
ただ、計算が終わってから計算し直すことはもちろん大切ですが、「確かめながら」計算することが有効です。
計算が終わってからまちがいに気づくよりも、途中でミスに気付いて軌道修正したほうが手っ取り早いでしょう。
- 3.14の計算でこんな数を見かけたことがないな…
- 兄が弟に追い付いたのに、弟より速度が遅いのはおかしい…
- 問われているのは、みかんではなく、りんごの数か…
というように、計算し終わりや解答欄に答えを書く前に、いったん立ち止まって「確かめ」をするといいでしょう。
実際、テスト本番では「見直し」の時間が取れない場合もあります。

テストは常に時間との勝負やからな
「見直し」時間はアテにしないよう、子どもたちに伝えています。
それよりも一発で計算を合わせられる計算力をつけることが大切ですね。
点数への執着を持つ
ここまでいくつかの方法を紹介してきました。
ただ、そのテクニックを伝えても、使うか使わないかはその子次第になります。
「馬を水辺に連れていけても、水を飲ませることはできない」というたとえもありますよね…

何回言ったらわかるねん!
と、お母様・お父様は思っても、本人が点数への執着を持たない限り、なかなか行動を変えようとはしないでしょう。
本番の入試が始まってから「オレ、計算をていねいにやるわ!」とようやく気づいた子もいます…
ご家庭だけで解決できない場合には、塾の講師やプロ家庭教師に相談してみましょう。
すべてを抱え込まずに、外部の手を借りることで解決できることもあります。
まとめ:【中学受験算数】計算力の重要性!計算ミスの原因と解決策
計算ミスを減らすことは、かんたんそうに見えて、けっこう難しいトレーニングです。
まちがった計算方法が染みついている場合には、その修正に手こずるものです。
また、テクニック部分だけでなく、「本人にミスを減らす意識がない」というメンタルがからんでいることも、事態を複雑にしています。
塾の講師を巻き込み、家庭教師・個別指導も活用しながら、計算力をアップさせていきましょう!