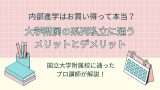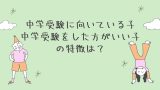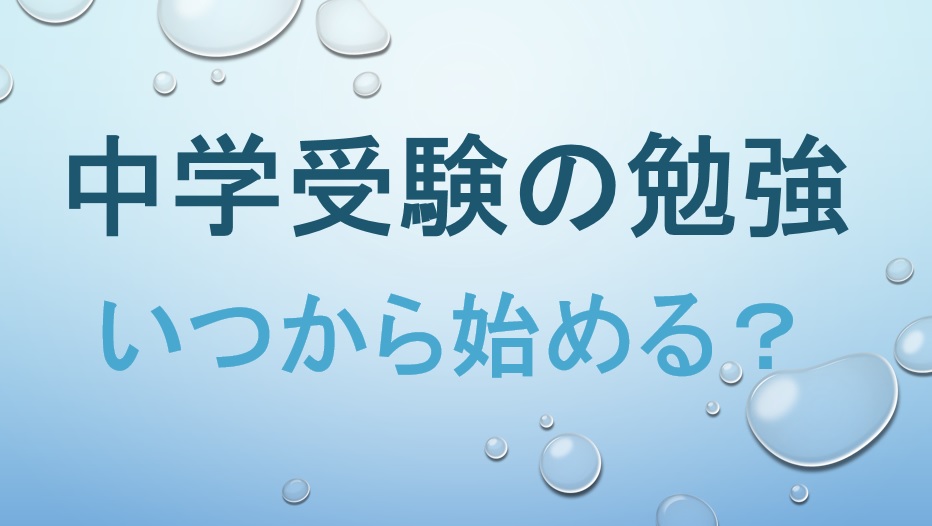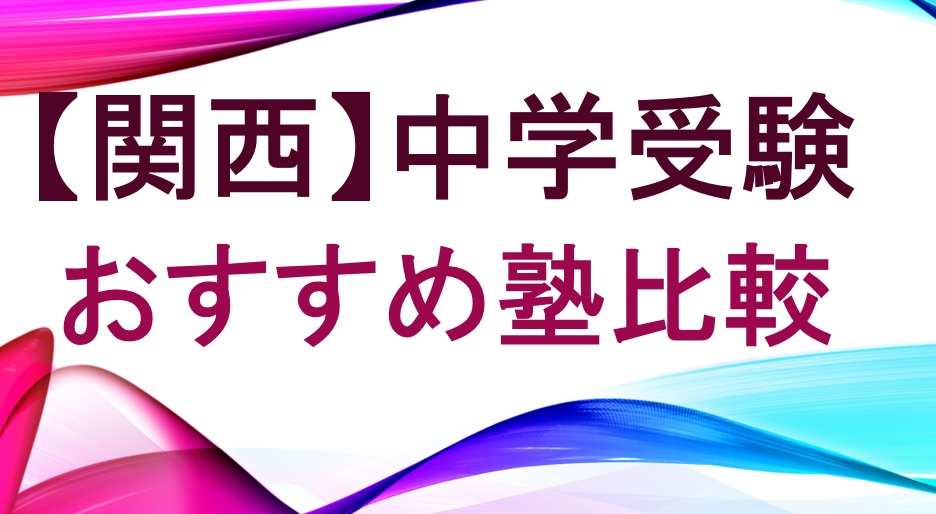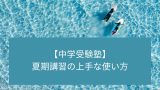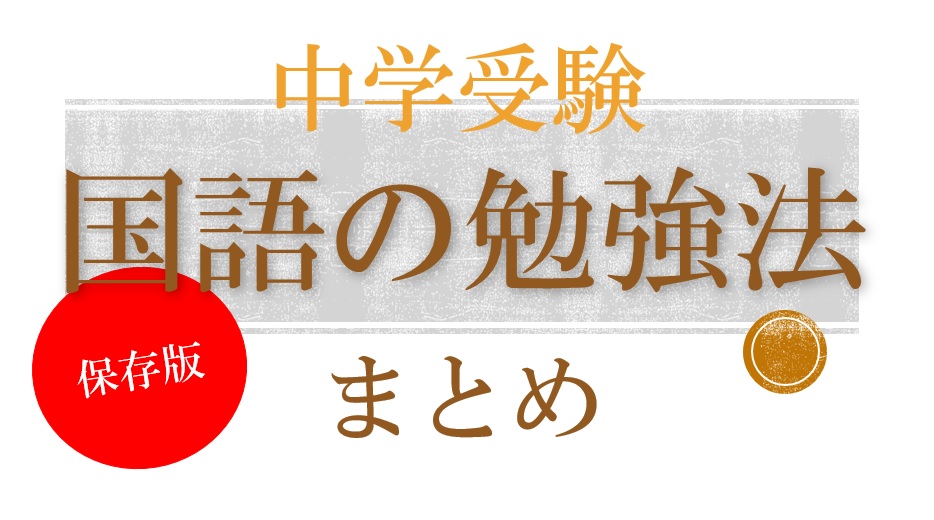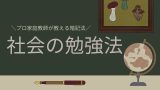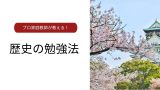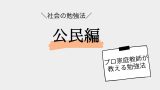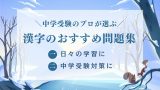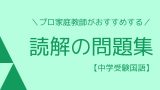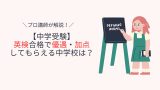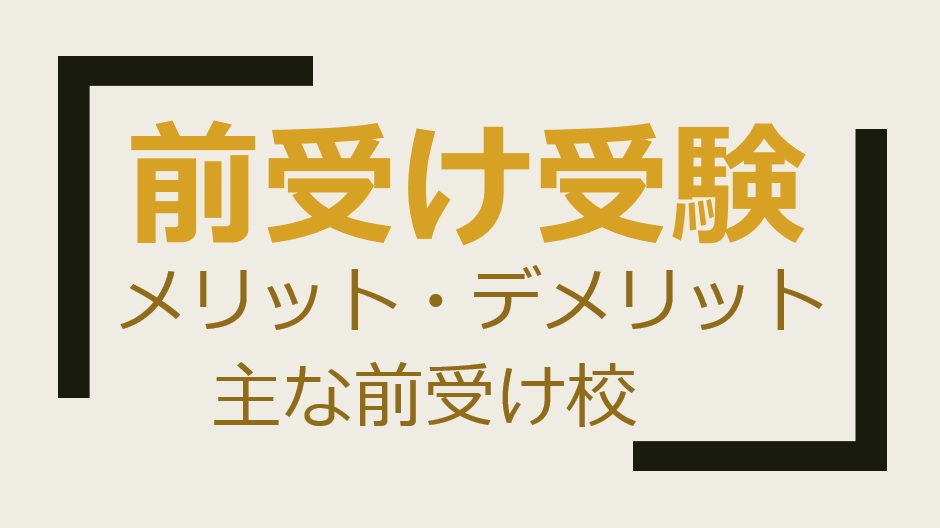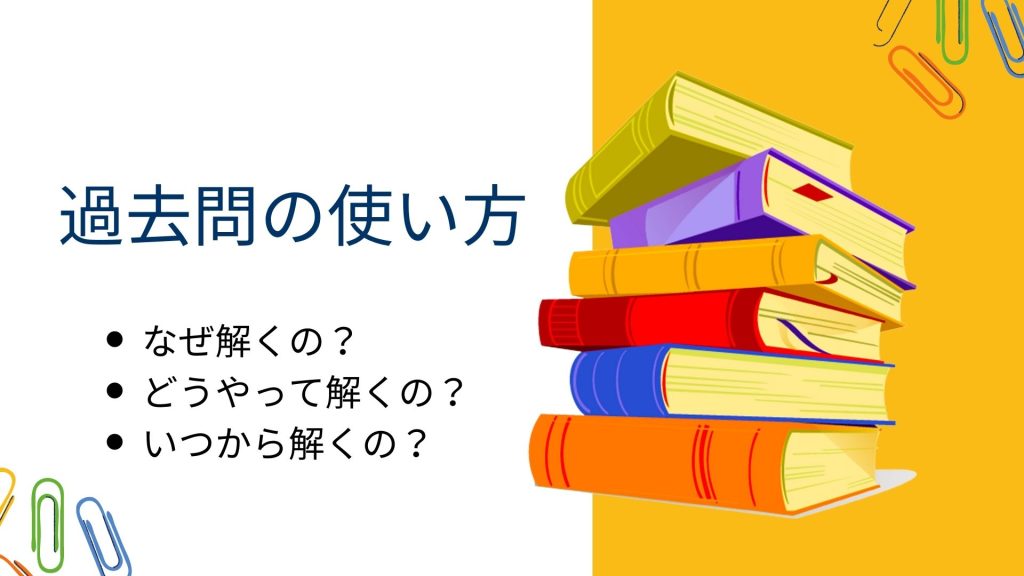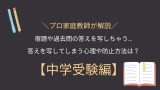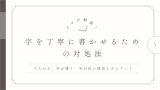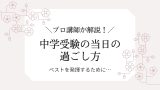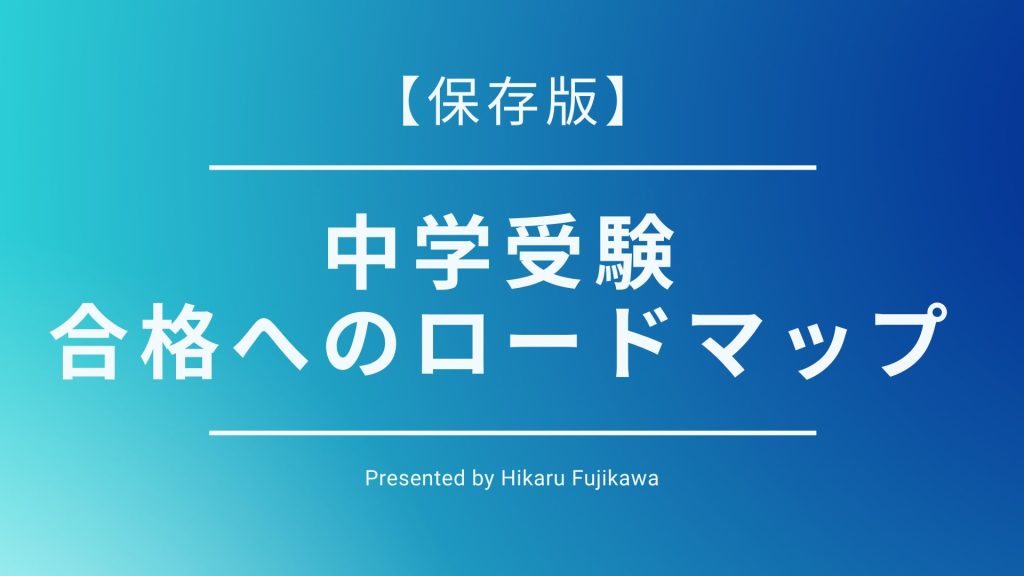
こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。

中学受験ってどうしたらいいの?
いろんな情報を聞くと迷ってしまう…
そのようにお悩みのお母様・お父様も多いのではないでしょうか?
当サイトでも、これまで中学受験に関する記事をたくさん書いてきました。
そこで、今回は中学受験に関する記事をまとめてみました!
- 中学受験をするメリット・デメリット
- 中学受験に向いている子・したほうがいい子の特徴
- 中学受験塾に入塾するタイミング
- 塾選びのポイント
- 中学受験塾の効果的な使い方
- 各教科の勉強法・おすすめ教材
- 受験校選びのポイント
- 中学入試の前日・当日の過ごし方
などなど、中学受験までの道のりの網羅した【保存版】です。
かなり長い記事になってしまったので、ブックマークしてご利用ください。
みなさんの志望校合格の一助になれば幸いです。

元塾講師・プロ家庭教師として、のべ1000人以上を担当してきたノウハウをお伝えします
中学受験のメリット・デメリット

中学受験をするべきなのか、中学受験をせずに地元の公立中学校に進むべきなのか、迷われているご家庭も多いはず。
まずは、中学受験をするメリットとデメリットを知っておきたいですよね。
中学受験をするメリットは…
- かわいい子には旅をさせることができる
- 少ない教科数で受験に挑戦できる
- 6年一貫で大学受験に臨める
- 学習環境や生活環境が整っている
といったところでしょう。
中学受験は「能力開発」的な部分もあります。
頭がやわらいかい小学生の間に、知識を身につけ、頭を使うトレーニングをすることができます。
また、高校受験や大学受験と比べて、少ない教科数で受験できるのもメリットです。
英語や評定・内申点も、中学受験ならあまり気にする必要はありません。

小学校の調査書が必要な中学校もありますし、英語受験・英検利用できる中学校も増えてきています
また、6年一貫の私立中学校では、前倒しのカリキュラムで授業が進みます。
ですので、6年一貫で余裕をもって大学受験に挑めます。
私立中学校は学習環境や生活環境が、整っているのも魅力でしょう。
「地元の公立は荒れていて、通わせたくない」というご家庭も多いですよね…
一方、中学受験をするデメリットは…
- 成長がゆっくりな子には不利
- 他の習い事は犠牲になってしまう
- 地元でのつながりがなくなってしまう
- 家庭の経済的な負担が大きい
ということです。
さきほど「中学受験には能力開発の意味合いも強い」と書きましたが、そのぶん、中学受験ではお子様にはけっこうな負荷がかかります。
成長がゆっくりな子には、しんどい経験になる可能性があります。
また、中学受験の勉強を優先しなければならない5・6年生になると、他の習い事を整理せざるを得ない場合も多いでしょう。
それに、中学受験でも進学先の私立中学校・高校でも、教育費がかかります。
事前に経済的なプランを立てておく必要もあります。
また、少し内容が重複しますが、6年一貫の私立中学校・高校のメリットとデメリットを知っておくといいですね。
地元の公立中に進んで高校受験をする場合と、どんな違いがあるのかを知っていると、中学受験するかどうかの1つの判断材料になります。
6年一貫校(主に私立中学校・高校)のメリットとデメリットについては、こちらの記事をどうぞ↓
また、大学附属の中学校は、一定の人気があります。
大学受験が難化している一方、中学受験の方が合格しやすい「お買い得」な系列校もあります。
大学附属の中学校については、こちらの記事をご覧ください↓
中学受験に向いている子・したほうがいい子の特徴

中学受験をするかどうか悩んでいる場合には、お子様が中学受験に向いているかをチェックしてみてもいいでしょう。
ただ、結論から言えば、「〇〇な子は中学受験に向いているor向いていない」と考える必要はないと、私は思っています。
なぜなら、中学受験を通して、子どもたちは成長するからです。
そして、おとなが思っている以上に、子どもたちは変わります。

実際、受験勉強をスタートしたときには標準的な成績だった子が、小6で「大化け」することはあります
とはいえ、中学受験の勉強をするうえで、「有利だな」と感じる小学生もいるのは事実です。
それは…
- 数字の感覚がある
- 言葉の感覚がある
という2点。
もちろん中学受験の勉強を通して、数字の感覚も言葉の感覚も磨かれていきます。
でも、受験勉強を始めるスタート時点で、けっこう差がついているものなんです…
中学受験の勉強でスタートダッシュをするには、数字と言葉の感覚があると有利でしょう。
一方、向いているかどうかではなく、中学受験をしたほうがいい子もいます。
それは…
- 早熟すぎる子
- 逆に勉強が苦手な子
- 教科による凸凹が大きい子
- 地元の友人とうまくいっていない子
です。
公立中学校でにはいろいろな学力の子がいます。
学校の先生は、平均層の子どもたちをメインに授業せざるをえません。
すると、早熟な子や勉強が苦手な子には、授業の進度や内容が合わない可能性が出てきます。
それならば、中学受験を経て、スタート地点である程度の学力の足並みがそろっている私立・国立中学校のほうが、その子に合ったレベルで学ぶことができるでしょう。

まあ、中高一貫の6年間で、また学力差が生まれるねんけどな
また、地元の同級生と関係がうまくいっていない子は、地元以外の選択肢として中学受験をする子もいます。
「地元の公立に行きたくない」という気持ちは、大きなモチベーションを生むこともあります。
中学受験に塾はマストか?

では、「中学受験をする」と決めた場合、塾は必須なのでしょうか?
私は…
塾に通ったほうが楽
だと考えています。
もちろん塾に通わずに中学受験にチャレンジすることはできます。
でも、お母様・お父様が中学受験への「道」を開拓しながら、合格へのロードマップを考えるのはとても大変です。
中学受験塾なら、合格に向けたシステムが整っています。
具体的には…
- 【学習】入試を見据えたカリキュラムで学習できる
- 【情報】学校情報や受験情報が手に入る
- 【時間】塾での勉強時間が長い
- 【仲間】競い合うことができる
という4点は、中学受験塾の大きなメリットでしょう。
先輩たちがたどってきた道が、合格への「近道」でもあります。
塾が提供してくれている「道」に乗っかってしまうのが、まずはおすすめです。

ただし、講座や宿題は、学年が上がるにつれて増えます。
塾に丸投げでなく、お子様にとって必要なものを取捨選択して、上手に利用することが大切です。
中学受験塾に入塾するベストなタイミング

では、いつごろから中学受験用の塾に通わせるべきなのでしょうか?
一般的には…
新小学4年生(小学3年生の2月)
と言われています。
中学受験の内容は、小学校の学習指導要領を大きく超えています。
ですので、4・5年生の間に基本的な知識とテクニックを身につけ、6年生では実戦力を磨いていくことになります。
また、中学入試は1・2月に実施されるため、塾での学年も2月から変わる塾がほとんどです。
ですので、中学受験をお考えの場合には、3年生の2月頃に塾に通い始めるように動き出すといいでしょう。
もちろん5年生・6年生からでも中学受験は可能です。
ただ、お子様にもご家庭にとっても、ハードな道のりになることは覚悟しておかなければなりません。
一方、低学年の段階から、ゴリゴリに中学受験塾に通わせたほうがいいかというと、私は疑問を感じます。
たしかにスタートダッシュは大事です。
低学年から塾に通っていれば、スムーズに受験勉強に移れるでしょう。
でも、低学年の間に、「勉強=苦痛」とお子様が感じてしまっては、元も子もありません。
低学年の間は、「勉強=楽しい!」と思える程度に、基礎学力を身につけられるといいですね。
塾選びのポイント

次に、塾選びのポイントをチェックしておきましょう。
お子様にあった中学受験塾を選ぶポイントは…
- 合格実績
- 学習システム
- 子どもとの相性
- サポート体制
- 費用
の5つです。
ご家庭が目指す志望校と、お子様の現状に合わせて、塾を選びましょう。
最難関の中学校を目指すのでなければ、ハイレベルな大手塾に通う必要はありません。
中堅中学校なら、地域密着塾・中小規模の塾でも合格できます。
また、お子様のレベルに合ったテキストや授業でなければ、せっかく塾に通っても空回りしてしまいます。
無料体験授業を受けられる場合には、参加してみましょう。

体験授業は「客寄せ授業」なので、すべてがわかるわけではありません。
塾の雰囲気や、お子様との相性を確認してくださいね。
また、追試や補習、質問対応などのサポート体制も、事前にチェックしておくといいでしょう。
もちろん通うにあたって、費用がどれくらいかかるのかも確認しておきましょう。
学年が上がるにつれて料金は上がり、6年生の頃には年間で100万円ちかくになる大手塾は多いです。
関西圏の大手塾6社を比較・まとめた記事はこちらです↓
関西にお住まいの方は、塾の比較にぜひご利用ください!
中学受験塾の効果的な使い方

では、中学受験塾とは、どのように付き合っていけばいいのでしょうか?
塾の効果的な使い方は…
- 受講目的をはっきりさせておく
- 塾・家庭の役割をはっきりさせておく
という2点です。
塾はいろいろなレベルの子が通っています。
習熟度別にクラス分けをしているとはいえ、すべての子どもたち・ご家庭を満足させることは難しいでしょう。
特に、最難関中学校の合格実績を確保したい塾としては、ハイレベルな教材・授業にせざるをえません。
すると、上位クラス以外の子どもたちにしわ寄せが来ます…
本来なら必要のない難しすぎる内容や、多くの宿題が課されてしまいがちです。

大手塾は「大食い客を満足させるために、一般の客にも特盛を食べさせている」って、よくたとえられますよね
特に6年生になると、オプション講座が増えます。
その講座や宿題をすべてこなそうとすると、パンクする可能性があります。
ですので、受講目的をはっきりとさせて、適度に間引く必要も出てくるでしょう。
また、塾とご家庭との、役割分担をしておくといいでしょう。
塾でインプットするだけで、すぐに成績が上がるわけではありません。
ご家庭で宿題・テスト対策をして、アウトプットするトレーニングをする必要があります。

そりゃ「塾に通う=即成績アップ」ではないわな
塾の言いなりになるのも、塾に丸投げするのもNGです。
「塾を上手に使いこなす」という意識で、塾と付き合うのがおすすめです!
特にハードになる夏期講習会の効果的な使い方については、こちらの記事をご覧ください↓
各教科の勉強法

ここからは、各教科の勉強方法について、説明していきます。
ただ、塾に通っている場合には、塾のカリキュラムや勉強法に乗っかることをおすすめしています。
塾ではこれまでの指導経験を活かして、独自のカリキュラムや教材を作っています。
そのカリキュラムや教材に合わせた勉強方法を、教えてくれるでしょう。
でも、お子様によっては、塾の勉強法が合う場合と合わない場合があります。
このサイトでお伝えする勉強方法は、通われている塾の講師とは、違った視点で解説している部分もあります。
「どちらかが正しいorまちがっている」という視点ではなく…
- 違った勉強法もある
- 塾のやり方が合わなかったら別のやり方を試してみる
というスタンスで、ぜひお読みくださいね!
国語の勉強法
まず、国語の勉強方法を見ていきましょう。
国語の力は大きく3つに分かれます。
- ボキャブラリー(語彙)
- 読む力
- 解く力
の3つです。
特に重要なのは、ボキャブラリー(語彙)、つまり、「知っている言葉」です。
小学生は常に発展途上です。
生まれてまだ10年前後ですから、常にボキャブラリーが不足している状態で、国語の読解問題を解かなければなりません。
ですので、日常生活や漢字・言葉の学習を通して、たくさんの言葉を身につけておきましょう。
ボキャブラリーは「武器」です。
1つでもたくさん持っているほど、読解問題で戦いやすくなります。

知っている言葉が多いほど、文章は読みやすく解きやすくなります。
語彙力を増やす方法をについて、くわしくはこちらの記事もご覧ください↓
また、「読む力」もトレーニングで高めていきましょう。
さきほど書いた通り、小学生は知らない言葉が多い状態で、難しい説明文や物語文、随筆文を読みこなさなければなりません。
ということは、「言葉をあまり知らない」という大前提で、読むトレーニングを積まなければなりません。
そのためにも…
- 論の展開
- 筆者の主張
- 登場人物の気持ち
を読み取っていく必要があります。
塾でも、こういった読むためのテクニックを教わりますよね。
トレーニング方法についてここに書き始めると、別のまとめ記事ができ上ってしまうので、こちらに【保存版】まとめ記事を用意しました↓
また、「解く力」も身につけていかなければなりません。
中学受験の国語の読解問題では…
- 記号選択問題
- 抜き出し(書き抜き)問題
- 記述問題
といった形で出題されます。
それぞれの出題形式に合わせて、テクニックを知っておく必要があります。
塾でも手厚く指導されると思いますが、「読む力」とは別に「解く力」も身につけていきましょう。
算数の勉強法
中学受験の算数では、「旅人算」「ニュートン算」「植木算」といった応用問題が出題されます。
いわゆる「特殊算」や「古典算」と呼ばれる、中学受験特有の問題です。
小学校では学ばない内容なので、中学受験対策として知識とテクニックを身につけていく必要があります。

方程式をxとyを使わずに解くなんて、学校では習わへんやん
ただ、大前提として、計算力が必要になります。
もし計算力がなかったら、せっかく知識とテクニックを学んでも、うまく活かせません。
せっかく解く方がわかったとしても、計算でまちがってしまったら不正解になってしまいます。
また、計算に苦戦していると、結局何を求めているのか見失う子もいます。
つまり、脳の容量は、知識とテクニックを使いこなすために温存しておきましょう。
そのためにも、計算には、脳の容量をあまり使わないようにするのがポイントです。

スマホと同様、「データ通信容量」があるのは脳も同じ。
でも、脳には「ギガ使い放題」はない…
数多くの単元を学習しますが、1回の学習で身につくわけではありません。
塾のカリキュラムは、何度もくりかえして学ぶ「サイクル学習」が基本になっているはずです。
塾の季節講習会(夏期・冬期・春期)などは、復習カリキュラムになっている塾も多いでしょう。
国語と同じように、ますは塾のカリキュラムに乗っかるのがおすすめです。
塾の学習サイクルを活用して、各単元の問題を解けるように仕上げていきましょう。
社会の勉強法
「社会=暗記」のイメージが強いですよね。
実際、頭がやわらかい小学生の中には、苦もなく社会の知識を吸収していく子もいます。
ただ、単なる丸暗記は、覚えにくく、そして、忘れやすい…
ですので、次の手順を意識して、トレーニングをするといいでしょう。
- ストーリー(因果関係)を理解する
- 一問一答形式ですらすら答えが言える
- 一問一答形式ですらすら答えが書ける
- 練習問題・総合問題を解く
ストーリー(因果関係)を理解したほうが、覚えやすく、また、忘れにくくなります。
特に小学生はまだまだ論理の力が弱いので、丸暗記に頼りがちなので、注意しましょう。
また、漢字が苦手な小学生は、漢字の書き取りは後回しにしてかまいません。
まずは、一問一答形式ですらすら答えが「言える」ことから始めましょう。
そのあと、「書ける」練習をしたほうが効率的です。

漢字が得意な子は、いきなり「書ける」かどうかトレーニングをしてもいいでしょう
一問一答形式ですらすら答えが出てくるようになったら、練習問題を解き、いろいろな角度から知識をアウトプットしていきましょう。
最終的には、単元がごちゃ混ぜになった総合問題を解けるようにしていきます。
入試では「これは鎌倉時代の問題」「こっちは江戸時代」と教えてはくれません。
自力で、どの単元の知識が問われているのかを判断しなければなりません。
総合問題を解きながら、頭の中の「引き出し」に知識を整理し直していくのが、入試に向けてのコツです。
暗記のコツについては、こちらの記事をご覧ください↓
また、各分野の勉強の記事はこちら↓
<地理>
<歴史>
<公民>
勉強法ではありませんが、関西圏の中学受験では社会が4番手扱いにされていることについての記事です。
関西圏で社会を勉強して4教科受験するか、社会を捨てて3教科受験をするか迷っているかたは、ぜひご覧ください↓
理科の勉強法
※現在、整備中(私自身が理科を担当していません…いずれ理科のプロに執筆・監修をお願いしたいと考えていますので、お待ちくださいませ)
各教科のおすすめ問題集・参考書
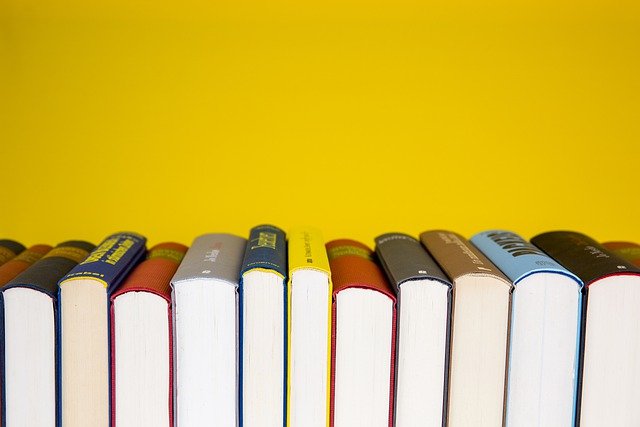

いい問題集や参考書って、何かありませんか?
おすすめは?
お母様・お父様から、そのように相談されることがよくあります。
そう質問されたときの私の定番の答えは…
まずは塾の教材をしゃぶり尽くしましょう
です。
塾が自信を持って、販売しているテキストなのですから、合格に向けての大切なエッセンスが詰まっています。
ですので、まずは塾のテキストを仕上げるようにしましょう。

中には、その時点で解けなくてもいい難問もあるので、選別は必要です
ただ、その子にとって、塾のテキストのレベルが合っていない場合や、塾のテキストをクリアして、さらに問題を「おかわり」したい場合には、市販の教材を利用するといいでしょう。
各教科のおすすめ教材・参考書をご紹介していきます!
国語のおすすめの問題集・参考書
国語はさきほどご紹介した通り、ボキャブラリー(語彙)が大切です。
日常生活を通して、言葉を身につけていくのが理想です。
でも、会話やテレビ、読書で身につける語彙にも限界や偏りがありますよね…
その場合には、ボキャブラリー(語彙)の参考書・問題集を活用するのもおすすめです↓
また、「漢字の読み書き」も、大切なボキャブラリーの一部です。
漢字の読み書きがままならないと、文章を読んで理解することも難しいでしょう。
小学校の漢字ドリルや塾の漢字教材も、しっかり使い込んでくださいね!
日々の学習に、また、入試対策に漢字の問題集をお探しの場合には、こちらの記事をどうぞ↓
「読解」を苦手にしているお子様も多いものです。
塾のテキストが、その子のレベルに合っていないことがよくあります。

私も小学生の頃、文章の内容がさっぱり理解できず、国語が足を引っ張っていましたよ…
その場合には、別の教材を使って、「読む力」「解く力」を鍛えるといいでしょう。
読解のおすすめ問題集・参考書に関する記事はこちらです↓
ただ、国語が苦手なのに、さらに解説を読んで理解するのは難しいでしょう。
国語が苦手なお子様ひとりでは、国語の独学はハードルが高い…
おとながサポートしてあげる必要がありますね。
算数のおすすめの問題集・参考書
※現在、整備中
社会のおすすめの問題集・参考書
さきほど「社会の勉強法」でお伝えした通り、社会は「ストーリー(因果関係)」を理解することが大切でした。
ただ、塾の教材って、重要なことが箇条書きになっているだけで、ストーリーが見えにくい構成になっていることが多いですよね。

塾の講師が、ストーリー(因果関係)をライブ授業で教えてくれるわけやねんけどな
また、塾の教材は、著作権の関係で、実物の写真があまり載せられていないものもあります。
そういう場合には、塾の教材だけでなく、市販の教材や学校の教科書・資料集も活用するといいでしょう。
社会のおすすめ問題集・参考書は、こちらの記事をどうぞ↓
他の教科でも同じですが、問題集は「1回解いて終わり」ではありません。
まちがい直しまでして、1冊の問題集をやりこむようにしましょう。
「あ、あのテキストの、あのページの、あの辺りに書いてあったぞ!」
なんて思えたら大成功です!
理科のおすすめの問題集・参考書
※現在、整備中(私自身が理科を担当していません…いずれ理科のプロに執筆・監修をお願いしたいと考えていますので、お待ちくださいませ)
志望校・受験校の選び方

6年生になると、だんだんと受験校を絞り込んでいく必要が出てきます。
受験校をしぼりこむヒントをお伝えしておきたいと思います。
受験校をしぼりこむコツは…
- 第1志望を軸にする
- 「すべり止め」を受けるか
- 後の日程になるほど偏差値は高くなる
- 体力と精神力を考慮する
の4点です。
もちろん第1志望の中学校の日程を最優先します。
また、いわゆる「すべり止め」を中学校を受けるかどうかも、考えましょう。
地元の公立中学校には行かないと決めているのであれば、納得のできる「合格安全圏」の中学校を確保しておきます。
つまり、「守り」の受験が必要です。
一方、「本命に不合格なら、地元の公立中学校に行く」と考えている場合には、「攻め」の受験だけでいいでしょう。

ここはご家庭でよく話し合って決めてくださいね
ただ、後の日程になるほど、合格しにくくなるので注意が必要です。
前半の日程で、中学校側は大半の合格者を囲ってしまいます。
ということは、後半の日程は、募集人数・合格人数が少なくなるのが普通です。
おまけに、偏差値が高い学校を受けた受験生が、後の日程ではレベルを下げて受験しにきます。
ですので、後の日程になるほど、合格の目安の偏差値がどうしても高くなってしまいます。
また、中学受験は、短期決戦の過密スケジュールです。
「受けられるだけ受ける」作戦では、お子様の体力と精神力がもたないこともあり得ます。
特に不合格が続くと、だんだんとしんどくなってきます…

受験生だけでなく、お母さん・お父さんのメンタルも大変やで…
ですので、体力と精神力を考慮した受験日程にしましょう。
受験スケジュールを考えるときには、塾が配る「受験カレンダー」などを参考にしましょう。
私は、ネット上で一般公開されている日能研の「偏差値一覧R4」をよく利用させてもらっています。
(私自身は、日能研とは無関係ですのでご安心を)
受験スケジュールの決め方や、日能研R4の使い方については、こちらの記事をどうぞ↓
【関西中学受験】というタイトルですが、日能研は全国展開している進学塾なので、全国の中学受験で使えますよ!(日能研さんありがとう)
プレテストを受験する
受験校を選ぶうえで、役に立つのが各中学校の「プレテスト」です。。
プレテストとは、中学校が独自で開催する模擬入試ですね。
最近では、多くの中学校がプレテストを実施しています。
だいたい2学期に入ってから実施されます。
プレテストには、ぜひ参加しておきましょう!
プレテストのメリットは…
- 入試本番を疑似体験できる
- 志望する受験生の中での自分の立ち位置がわかる
- 中学校との「つながり」ができる
という3点です。
何より、本番とほぼ同じ環境で、本番に似た問題を解くという経験を積めます。
また、自分が今どの位置にいるのか、はっきりとわかります。
一般的な模擬テストの志望校判定よりも、リアルに感じられるでしょう。
そして、学校との接点ができるのも、大きなメリットです。
プレテストの結果が良かった場合には、「特待生」の資格がもらえることもあります。
プレテストの結果が悪くても、学校の先生から直接アドバイスや入試のヒントがもらえるかもしれません。

過去問を解いて、プレテストにも真剣に臨みましょう!
検定・資格を利用して受験する
また、受験校を絞り込むうえで、検定や資格が役に立つこともあります。
最近、特に増えてきているのが、実用英語技能検定(英検)を利用した受験です。
「英検」の合格級によって、優遇してもらえる中学校が増えてきています。
具体的には…
- 加点してもらえる
- 得点に読み替えてもらえる
- そもそも出願資格になっている
などの優遇をしてもらえます。
もし英検で合格している級がある場合には、優遇してもらえる中学校を選ぶのもありでしょう。
また、受験科目として「英語」を選択して、英語受験できる学校も増えてきています。
小学校での英語学習が必修になり、これから英語を利用した中学入試はますます増えていくでしょう。
「英検利用」について、くわしくはこちらの記事をどうぞ↓
英検と並び、小学生がよく受検する検定として、日本漢字能力検定(漢検)があります。
ただ、結論から言うと、英検のほうが優遇・加点してもらえます…
中学受験の優遇・加点のために、漢検を受検する必要はないでしょう。
でも、漢字検定に向けて勉強して、漢字を身につけることは、中学受験にも大いに役に立ちます!
小学6年生までの漢字はしっかりと書ける必要があるのは当然です。
また、小学校では習わない漢字も読めておくと有利ですし、ボキャブラリー(語彙)を増やしておくだけで、文章が読みやすくなります。
ですので、漢字学習のペースメイクとして、漢字検定を活用するのがおすすめです。

検定を通して「合格」を経験しておけるのも、受験生にはメリットです
「前受け受験」で第1志望に備える
また、近年「前受け」をする受験生、「前受け」をすすめる塾が増えてきています。
「前受け受験」とは、12月頃から実施される入試を、第1志望の受験前に受けておくことです。
リハーサルの意味合いが強い受験です。
全国的には…
- 海陽中等教育学校(愛知)
- 愛光中学校(愛媛)
- 北嶺中学校(北海道)
などが有名です。
2月に中学受験が行われる首都圏の受験生にとっては、1月中旬に中学入試が解禁される関西の中学校も前受けの対象になりますね。
「前受け受験」のメリットは…
- 実際の入試で場慣れできる
- 合格して勢いに乗れる
という2点です。
やっぱり入試は、これまでの模擬テストとは違います。
急に緊張する子もいれば、自分の弱点にあらためて気づく子もいるでしょう。
第1志望の受験の前に、事前に中学入試を経験できるのは大きなメリットです。
また、前受け校で合格を経験することで、自信がつく受験生もいます。
1つでも「合格」を確保しておけば、落ち着いて第1志望の受験に臨めます。
ただ、前受けで不合格になると、入試直前に逆に勢いをそいでしまう可能性があります。
モチベーションを立て直すのに、お母様・お父様も苦労するでしょう。

入試直前に、落ち込みたくないやん
もちろん前受け受験は必須ではありません。
前受けせずに、第1志望の受験に臨む受験生もたくさんいます。
1つの選択肢として「前受け」するかどうか、ご家庭で決めておきましょう。
前受け受験について、くわしくはこちらの記事をどうぞ↓
過去問トレーニングを始める
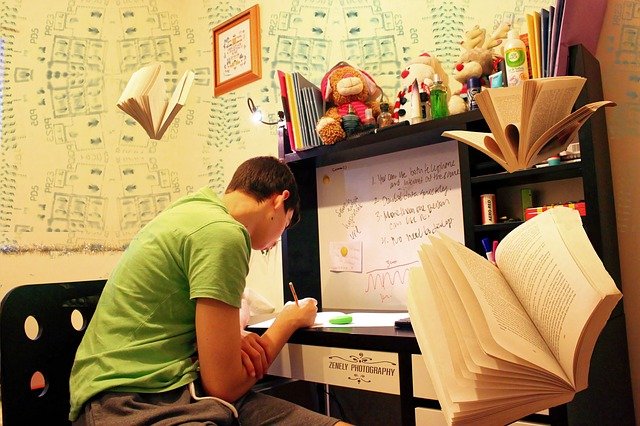
受験校がある程度しぼりこめたら、受験校の過去問を解いていきます。
過去問に手を付け時期としては、各教科の知識がだんだんと定着してくる、6年生の夏休み以降がいいでしょう。
ただ、過去問を解くときには、必ず守らなければならないポイントがあります。
それは…
- 入試本番のつもりで解く
- 厳しく丸つけ・採点する
- まちがいの教訓を次の年度に活かす
の3点です。
まず、入試本番を想定して、過去問を解きましょう。
当然、模範解答を見たり、テキストの解説を読みながら答えてもいけません。
時間も正確にはかり、緊張感を持って、演習します。
そして、丸つけや採点も、厳しめにおこないましょう。
お子様自身が丸つけをすると、甘くなってしまいがちなので、お母様・お父様が丸つけ・採点をするといいでしょう。

点数をごまかしたくなる受験生がよくいます…
でも、何の得にもならないのでやめましょう。
まちがった問題については、次の年度、そして、入試本番に、その反省を活かせるようにしましょう。
ルールを守って過去問でトレーニングして、本番の入試に備えましょう!
過去問の演習について、くわしくはこちらの記事をどうぞ↓
ただ、小学生は、まだまだ自分を律するほどには成熟していません。
ついつい魔が差して、というか、悪気なく答えを写してしまう子や点数をごまかしてしまう子は、たくさんいます。
過去問演習で答えを写されると、せっかくの過去問の意味がなくなってしまいます…
子どもたちが答えを写してしまう心理・理由や、その防止法をまとめた記事はこちらです↓
また、中には「字が雑すぎて読めない」という子も多いでしょう。
受験では字が雑だと損することが多いです(不正解にされる可能性が高くなります…)。
また、自分自身が読み間違えて、自分が損することもけっこう多いものです。
字をていねいに書かせるための声掛けについて、まとめた記事はこちらです↓
中学入試の前日・当日の過ごし方
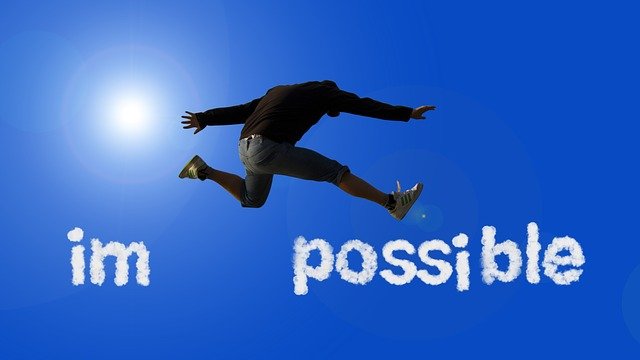
いよいよ入試直前です。
あとは入試本番で、自分のベストを発揮するだけです。
では、試験会場で実力を出し切るためには、入試前日にどのように過ごせばいいのでしょうか?
入試の前日には…
- 早起き・早寝
- 持ち物を準備する
- これまでの知識・テクニックを復習する
- できるだけいつも通りに過ごす
ことを心がけましょう。
入試本番に、朝から頭をフル回転させるために、前日にも早起きしておきましょう。
そうすれば、前日の夜に寝やすくなります。

寝られへんかったら、余計に緊張しそうやん
また、新しい教材に手を付けたり、難しい問題を解いたりするのはやめましょう。
今まで使い込んできたテキストを復習して、知識とテクニックをチェックしましょう。
「入試前日だから!」と、特別なことをする必要はありません。
落ち着いて、入試当日を迎えられることが1番です。
やってはいけないNGな前日の過ごし方は、こちらの記事をどうぞ↓
中学入試の当日も同じです。
試験会場で落ち着いて過ごせるように心がけましょう。
具体的には…
- 早起きする
- 目覚めの問題を解く
- 持ち物の最終チェックをする
- 余裕をもって会場に着く
- 心はホットに頭はクールに
- 休み時間に答え合わせをしない
- 早寝する
という7つのルールがおすすめです。
まあ、かんたんにまとめると、「入試で実力を発揮する以外に、余計な労力は使わない」ってことです。
「心はホットに頭はクールに」というルールが、1つだけ抽象的ですよね。
中学受験の怖いところは、本番に番狂わせはよく起きることです…
合格できると思っていた子が、大コケした…不合格だと思っていた子が、自己ベストをたたき出す!
そういうことが中学受験では起こります。

小学生がまだまだ成熟していませんし、内申や評定による「持ち点」がないからです
「合格したい」という強い気持ちが、本当に合格を手繰り寄せることがあります。
一方で、気持ちが熱くなりすぎると、焦りに変わってしまいます。
「心はホットに頭はクールに」、いい緊張感をもって、入試問題に取り組んでくださいね!
入試当日の過ごし方についての特集記事はこちらです↓
最後に…
「中学受験合格へのロードマップ」をまとめてみましたが、長すぎるまとめ記事になってしまいました…

ぜひブックマークして、必要に応じてお読みください!
長い記事になった一方で、「まだまだ書き足りない」「伝えきれていない」と感じています。
最後に1つだけ、受験生やお母様・お父様にお伝えするとしたら、中学受験を通して…
ハッピーな人生を送ってほしい
ということです。
中学受験に合格しても、不合格であっても、人生はまだまだ続きます。
つまり、中学受験は「目標」であっても、「目的」ではありません。
中学受験を経て…
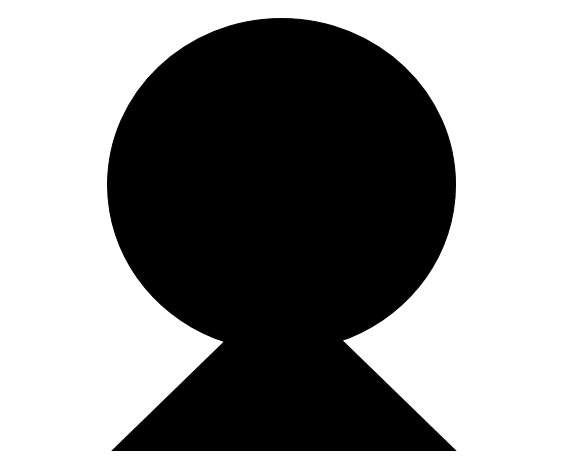
中学受験しなければよかった…
あのとき別の中学校に行っていれば…
と、子どもたちに後悔だけはしてほしくありません。
すぐには実感できなくてもいいんです。
おとなになったときに…
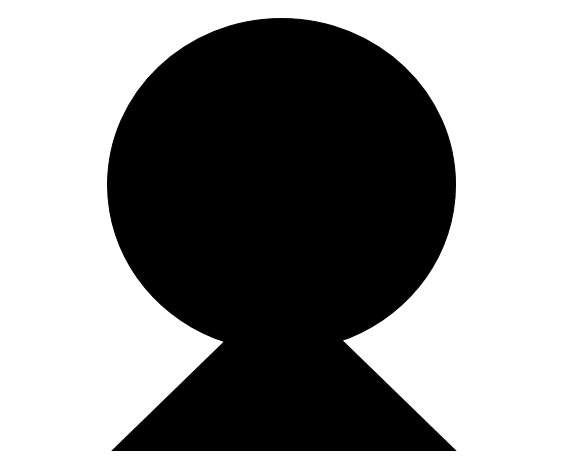
中学受験したから、あの人たちに会えたんだな。
この中学校・高校に行ってよかったかも
って、ほんのりとでも思ってもらえたらいいなと、私は感じています。
私自身にも子どもが生まれ「ハッピーな人生を送ってほしい」という気持ちは、塾講師をしていた時代よりも強くなりました。
このサイトに訪れ、記事を読んでくださった皆様が、納得のいく中学受験を迎えられることを祈っています。