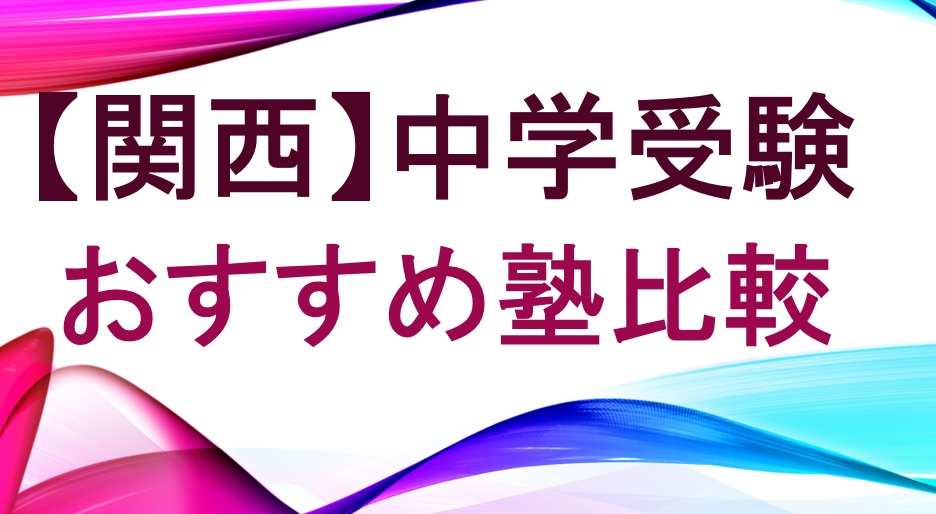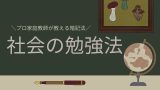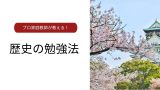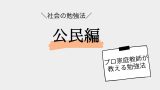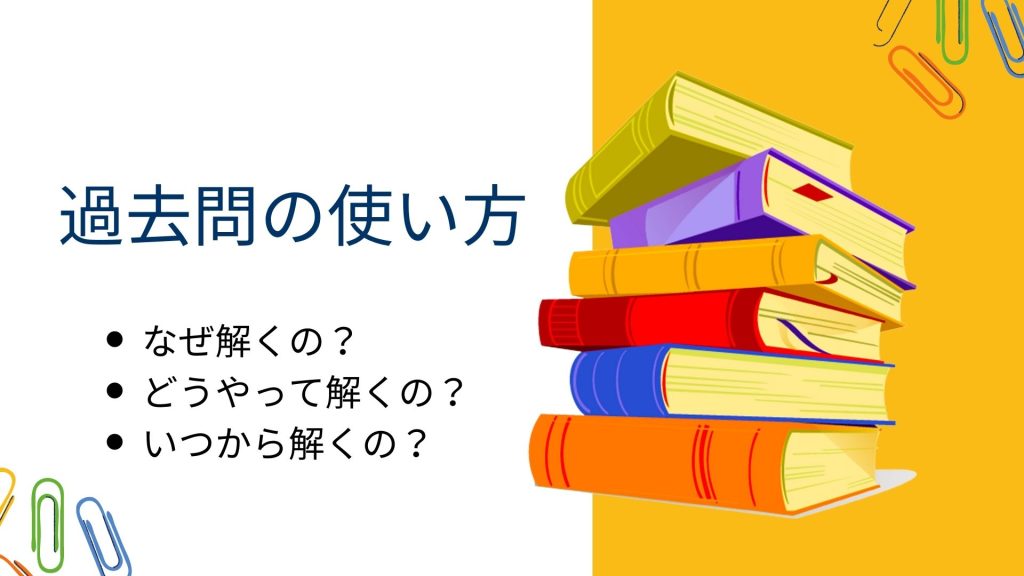こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。
中学受験といえば、算数・国語・理科・社会の4教科がメインですよね。
でも…

関西では、社会って4番手やんな…
暗記するだけやし、後回しにして大丈夫ちゃう?
そのように悩んでいるお母様・お父様も多いのではないでしょうか?
今回の記事では…
- 関西圏の中学受験で社会が後回しにされる理由
- 社会は後回しにして大丈夫か
- いつ社会を勉強するべきか
がわかります。
勉強で後回しにされるだけでなく、社会を外して3教科受験が主流になっている昨今…
社会の扱い方について、いっしょに考えていきましょう!

元塾講師・プロ家庭教師として、のべ1000人以上を担当してきたノウハウをお伝えします
【関西圏の中学受験】なんで社会は後回しにされるの?

まず、社会が後回しにされてしまう原因から考えていきましょう。
社会が後回しにされるようになった理由は…
- 関西圏では3教科受験が主流
- 6年からでも間に合うと思われがち
の2点でしょう。
1つずつ見ていきますね。
関西圏では3教科受験が主流
関東の中学受験では、今でも4教科受験、つまり、算数・国語・理科・社会がメインだそうです。
でも、関西圏の中学受験では、3教科受験、つまり、算数・国語・理科が主要3教科となっています。
そう、社会は完全に「4番手扱い」です…

社会科も担当する私としては寂しいばかりです…
社会は「選択講座」、オプション扱いという中学受験塾がほとんどです。
それは、関西圏のトップ校である灘中学校や甲陽学院中学校が、算・国・理の3教科受験であることが影響していると思われます。
トップ校が3教科受験であれば、それらを追う難関校も3教科でも受験できるようにせざるを得ませんよね。

「4教科受験なら受験しない」と言われたらイヤやもんな
中には、経営上の都合から「3教科でうちの学校は受験できますよ!」とお手軽さをアピールしたい中学校もあるでしょうが…
関西圏での4教科受験のメリットとデメリットについては、こちらの記事をどうぞ↓
6年からでも間に合うと思われがち
算数は、いわゆる「積み上げ型」の教科です。
例えば、「割合」を習った後、「割合」を使って、「相当算」「食塩水」「売買」などの問題を学習します。
つまり、「積み上げ型」の教科では、手順を踏んで、トレーニングを積まなければなりません。

手前でつまずくと、その先がわからなくなってしまうのが「積み上げ型」の怖いところやな
また、国語という教科は、総合力です。
英語もそうですが、言語の学習というのは「壮大な慣れ」でもあります。
経験の少ない小学生が、文章を読むために必要な語彙(ボキャブラリー)を身につけ、一般的・社会的な知識を知るには、時間がかかりますね。
理科は、物理・化学・生物・地学に分かれます。
さらに、知識の暗記だけでなく、目に見えない現象の理解、そして、計算も必要とされます。
それに比べて社会科は、「覚えてナンボ」の面が強いですよね。
だから、
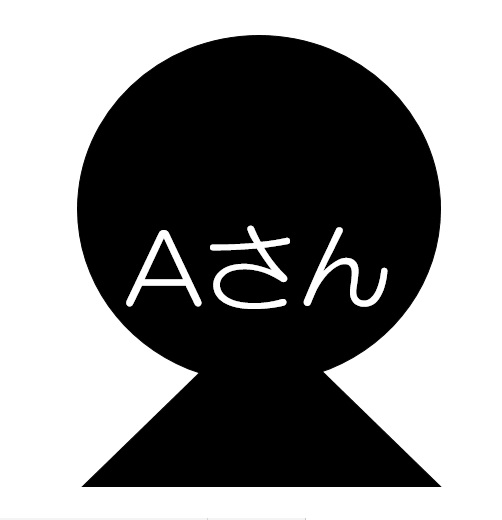
社会は暗記さえすればいいから楽勝やん!
と思われがちです。
子どもたちだけでなく、「社会は6年生になってから詰め込めば何とかなる」と考えているお母様・お父様も多いものです。
※関西圏の中学受験塾を比較した記事はこちらです↓
でも社会は後回しにするべきじゃない!
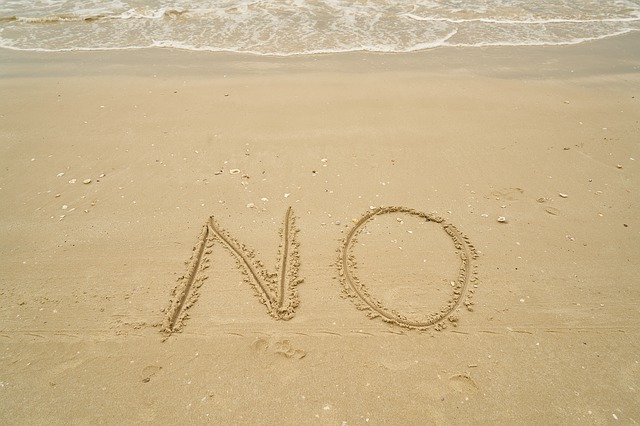
実際には、社会は後回しにするのはオススメできません!
社会を後回しにすべきじゃない理由は…
- 下地がないと小6からでは間に合わない
- 社会だけに集中できるわけではない
の2つだと、私は考えています。
もう少しくわしく見ていきましょう!
下地がないと小6からでは間に合わない
以前…
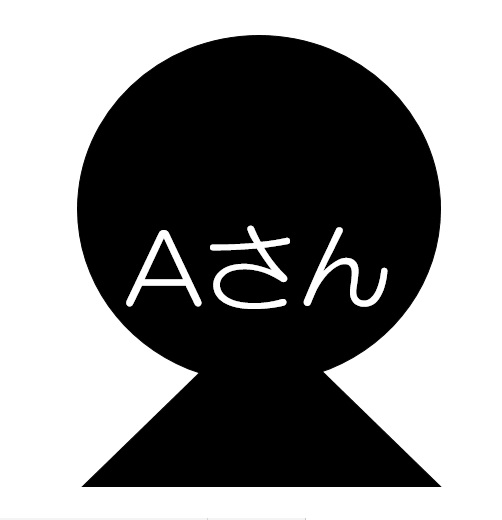
社会は6年生になってから本気出す
と言っていた男の子がいました。
でも、本腰を入れて社会を勉強しようと考えて、私に依頼が来たのは、6年生の夏ごろ。
「勉強しなければ」とは思いつつも、やはり苦手な社会を、ズルズルと夏まで後回しにしていたそうです。
本人としては、夏休みの間に、社会をマスターできると考えていたようでした。
実際に指導を始めてみると、都道府県の位置も名前もあやふや…
歴史の時代の流れも、主要な登場人物・できごともほとんど覚えていませんでした。

これはまずい…
そう思った私は、現状をお母様・お父様にもお話しし、かなり急ピッチに課題をこなさなければならないことをお伝えしました。
手始めに、都道府県の位置と名前を、次の週までに暗記してくるように課題を出しました。
1週間後、私が「じゃあ、都道府県テストをしようか」と言うと…
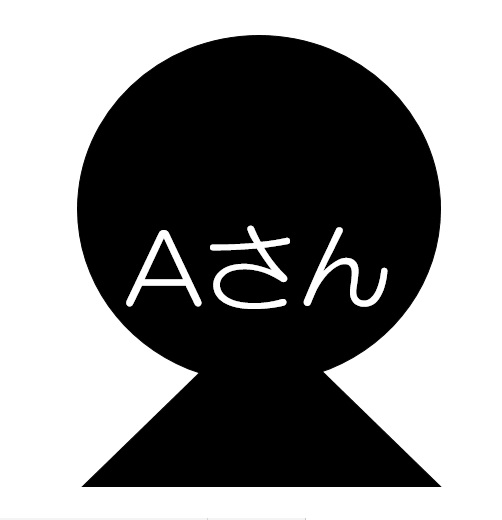
覚えられへんかった
と言って、いろいろな言い訳を口にしました。
本人だけでなく、お母様・お父様にも事情を聞いてみると…

社会に回す時間はあったけれど、結局は好き嫌いで勉強して、後回しになったみたいです
とのことでした。
他の教科の暗記事項は頭に入っているので、暗記が苦手というわけではありません。
また、都道府県の名前と位置の暗記の練習方法は、事前に伝えていたので、やり方がわからなかったわけでもありません。
地理だけでなく、歴史の暗記課題を課したときも、結果は似たようなものでした。
その後、指導自体は楽しんでくれて、授業を通して、地理と歴史の知識を急速に吸収してはくれました。
でも、結局は夏休みの間に、社会をマスターするまでには至りませんでした。
その子は結局、社会をあきらめて、算数・国語・理科の3教科受験をしました。
お父様は…

社会は中学に入ってからも必要なので、勉強できてよかったです
とは言ってくれました。
でも、本人もお母様・お父様も、そして、私も…

もっと早く社会に本腰を入れていれば…
と思わずにはいられませんでした。
社会は暗記すれば、得点しやすい教科であることは事実です。
ただ、覚えなければならない知識はかなりの量です。
小学6年生になるまでに社会の基礎ができている場合には、小6ではその知識に「肉付け」していくことができます。
でも、6年生になるまでに社会の基礎ができていない場合には、6年生になってから下地作りをしなければなりません。
社会の勉強法・暗記法について、くわしくはこちらの記事をご覧ください↓
社会だけに集中できるわけではない
社会を後回しにすべきでない理由の2つ目は、「6年生は忙しいから」です。
さきほど紹介したエピソードの男の子もそうですが、5年生までの間には…
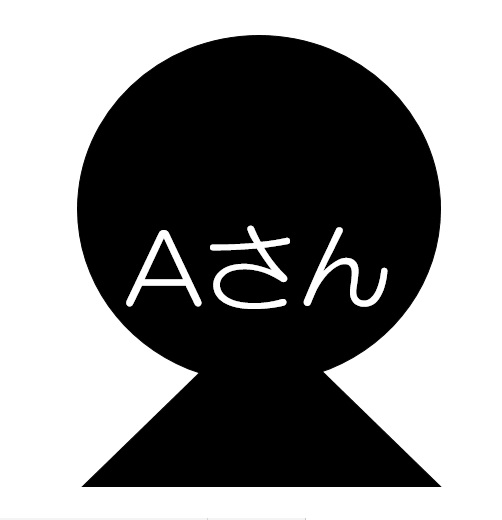
社会は6年生になってから本気出す
と思ってしまうのは、よくわかります。
なぜなら、5年生までのスケジュールは、まだまだ余裕があるからです。
でも、実際には、5年生の2月から新6年生として、塾で授業をスタートしてみると…
- 授業時間数が増える…
- それに合わせて、宿題も増える…
- 日曜日には特訓授業が始まる…
- さらにその特訓授業の宿題も増える…
- 季節講習会は、朝から晩まで塾…
6年生になると、塾のスケジュールをこなすだけで精一杯という状況になりがちです。
社会にだけ時間をかけられるのなら、6年生になってから取り組んでも間に合うかもしれません。
でも、実際には算数の難問を解かなければなりませんし、国語の文章を読むには時間がかかります。
もちろん理科の仕上げもしなければなりません…
時間は限りある資源です。
結局は、6年生になってからも、社会の勉強は後回しになってしまう可能性大なのです。
むしろ5年生までに社会の基礎を固めておくのが正解!

国語や算数は、出題内容によって、点数の波が出やすいでしょう。
また、時間との勝負になるので、常に時間配分に注意しなければなりません。
理科は、単元の幅が広く、得意単元・苦手単元の出題バランスによって、点数が左右されがちです。
でも、社会のテストで「時間切れ」になることは、ほぼないでしょう。
また、一問一答形式で覚えた知識が、テストでそのまま問われることもかなり多くあります。
つまり…
社会は覚えれば覚えるだけ点数が安定する「おいしい教科」
です!
そんな「おいしい」社会は、6年生になるまでに、味方につけておいたほうがお得です。
さきほどお伝えした通り、6年生になってから、社会だけに集中できる時間はそれほど取れません。
ですので、社会は比較的時間の余裕がある5年生までの間に、基礎固めをしておくのが正解です!
では、どのタイミングで社会を学習しておけばいいのか、スケジュールをチェックしていきましょう。
中学受験の社会のおすすめ問題集・参考書についてはこちらの記事をどうぞ↓
【小学4年生】「地理」の下地を作っておく
まず、4年生までの間に、「地理」の下地を作っておきましょう。
手っ取り早い方法は、塾の社会の講座を受講することです。
塾は、合格に向けての逆算した効率的なカリキュラムを作ってくれています。
そのカリキュラムを活用することが、合格への近道とも言えます。

最近は、4年生の間は、社会のクラスは開講せず、映像授業のみという塾が増えてきています(残念…)
地理の学習の内容は、
地名の暗記
都道府県・県庁所在地・山地・山脈・平野・半島・島・海・海流・川など
系統地理
気候・農業・工業・林業・水産業・環境問題など
地誌
九州地方(沖縄含む)・中国四国地方・近畿地方・中部地方・関東地方・東北地方(北海道含む)など
これらの地理の基礎を、楽しみながら学んでいきましょう。
ただし、地理が好きで、下地ができている場合には、必ずしも塾の授業を受講しなくてもいいでしょう。
地理のテキスト・問題集だけを購入して、家庭学習しておくのもアリです。
そして5年生になってから、しっかりと地理の知識を固めていきましょう。
地理の勉強法について、くわしくはこちらの記事をご覧ください↓
【小学5年生】「歴史」の下地を作っておく
小学5年生の間に、塾ではひととおりの地理の学習が終わります。
地理の知識を固めるのはもちろん重要ですが、5年生の間に、「歴史」の下地を作っておくことが大切になります。
そのためにも5年生では、塾の社会の授業は必ず受講することをオススメしています。
なぜなら、塾では入試に向けて綿密にカリキュラムを組んでくれているからです。
授業では主に歴史の学習を進めながら、宿題や公開テスト対策として、地理の復習のカリキュラムを組んでいます。
復習、つまり、サイクル学習のカリキュラムを、自分自身で作るのは難しいですよね。
塾のカリキュラムという「レール」に乗った方が、学習はずっと楽になるでしょう。

我流で勉強するのも限界があるよな
歴史の勉強をするときには、「歴史の流れ」を意識しながら学習しましょう。
言い換えると、歴史の「ストーリー(因果関係)」をつかむのがポイントということです。
社会はともすれば、暗記に頼ってしまいがちです。
でも、ただただ単なる暗記に頼ってしまっては、知識がバラバラで散らばってしまいます。
それでは、覚えにくいですし、忘れてしまいやすいでしょう。

「暗記=かんたん」とは限りません
だからこそ、「歴史の流れ=ストーリー(因果関係)」を理解しましょう。
例えば、平安時代なら…
奈良時代はお坊さん(僧)が政治に口出ししてきた
↓
だから都を平安京に移して、桓武天皇は天皇中心の政治を再び目指した
↓
空海や最澄というお坊さんは、山の中で修行する宗教を始めて、政治には口出ししなくなった
↓
でも、貴族・藤原氏が自分の娘を天皇と結婚させて実権を握った(摂関政治)
↓
藤原氏よりも権力を持つためには、天皇よりもレベルアップした上皇になるしかない(院政)
↓
天皇と上皇がケンカすると、ケンカの専門家である武士が活躍する
↓
そして、とうとう平清盛が武士として初めて太政大臣に上りつめた
このように、たくさんの人物が権力を奪い合う長い長い平安時代も、因果関係をつかむことで、ストーリーを理解しやすくなります。
ストーリーを理解しておけば、知識を肉付けしやすくなるので、記憶が定着しやすくなります。
歴史の勉強法について、くわしくはこちらの記事をご覧ください↓
【小学6年生の夏まで】「公民」を学びながら「地理・歴史」の復習
塾では6年生になると、歴史の学習を終わらせ、「公民」がスタートします。
憲法や政治、経済について学ぶ分野ですね。
でも、小6の公開テストや模試では、まだまだ地理や歴史が出題されます。
ですので、6年生になって公民の学習を進めながらも、地理・歴史の復習を進めておかなければなりません。
また、入試でも、公民の割合よりも、地理・歴史を多く出題する中学校はたくさんあります。

なおさら小5までの勉強が大切やな
6年生になってからも、基本的には塾のカリキュラムの沿うと、地理・歴史を復習しやすいでしょう。
公開テストなどの模擬テストの出題範囲に合わせて、復習するのもオススメです。
テスト結果が返ってきたら、まちがい直しをして、苦手単元をあぶり出し、1つ1つ克服すると効果的ですね。
公民の勉強法について、くわしくはこちらの記事をご覧ください↓
【小学6年生の夏以降】入試問題などの総合問題でアウトプット
夏休みの間に、地理・歴史・公民の土台をある程度固めてしまいましょう。
そして、夏休みを終えると、いよいよ「過去問演習」がスタートします。
過去問などの入試問題では、出題範囲はもちろん…
全単元
ですよね。
「九州地方が出題されるよ」とか「江戸時代がテストに出ます」とか、教えてもらえませんよね。
ですので、単元と単元がごちゃ混ぜにされた総合問題で知識をアウトプットできなければなりません。
スポーツでもどんなに基礎練習をしていても、試合などの実戦をしてみないと、基礎練習で身につけた技術が本当に使えるかどうかはわかりませんよね。

勉強もスポーツと同じやな
入試問題という実戦形式の問題を解くことによって、これまで身につけた知識を使えるようにトレーニングしていきます。
過去問でまちがった内容は、自分の弱点でもあり、「伸びしろ」でもあります。
覚え直しをして、類題が出題される次の機会に、きちんと得点できるようにしておきましょう。
また、過去問を解くことで、その学校の出題傾向がつかめてきます。
例えば、大阪府南部の難関校・清風南海中学校の社会を解いて…
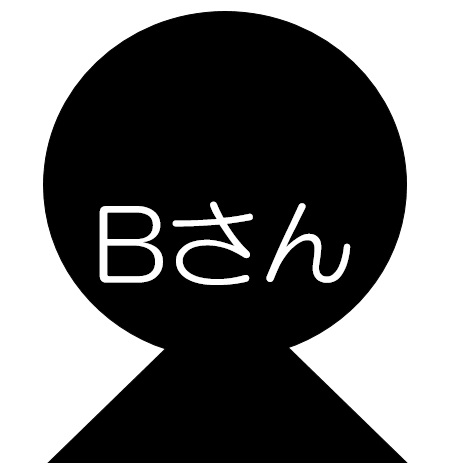
社会やのに、計算問題出てくるやん!
時代のならびかえ問題が細かくて難しい…
世界地理を出題するなんて、反則やわ…
というように、その学校の出題傾向をつかむことができます。
「敵を知る」ことは大事ですね。
出題傾向をつかんだら、対策も立てやすくなります。
過去問トレーニングの方法について、くわしくはこちらの記事をご覧ください↓
まとめ:社会の勉強を後回しにして大丈夫?
関西の中学受験では、社会はどうしても4番手扱いです。
でも、社会は覚えたら点数が安定しやすい「おいしい教科」です。
そんな「おいしい教科」である社会を、後回しにしてしまうのはもったいない!
ぜひ、4年生・5年生の間から、基礎固めしておき、6年生になってから「頼れる武器」になってもらいましょう。