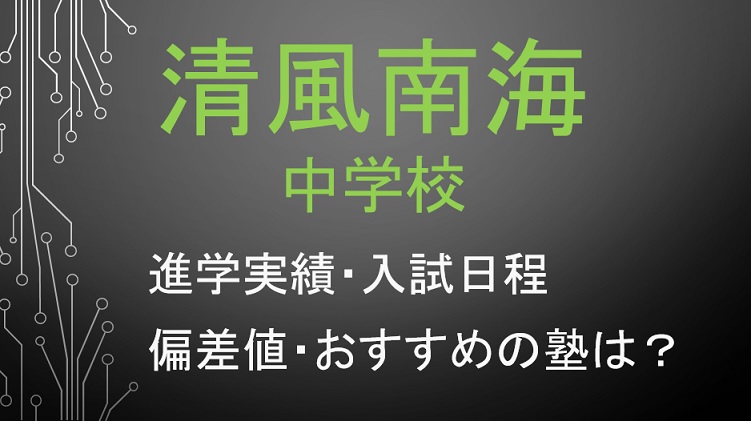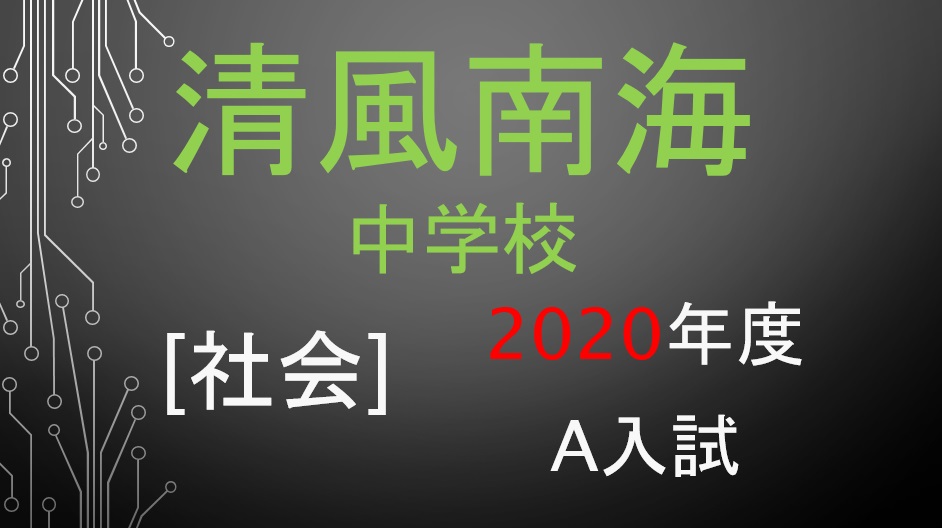
こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。
中堅校レベルまでの社会の入試問題は、一問一答形式が中心で、基本的な知識を直球で問われます。
一方、難関校レベルになってくると、一問一答形式ではなく、年代のならびかえや正誤問題、資料の読み取り問題などを通して、知っている知識をどう「使う」かが問われます。
難関校レベルの受験生に、一問一答形式で出題すると、かんたんに解けてしまいます。
ですので、学校側もいかに問題を複雑にするか、頭を悩ませていることでしょう…
今回は、知識の応用力が問われる学校の1つ、清風南海中学校<2020年度A入試>の社会の入試問題をご紹介します!

元塾講師・プロ家庭教師として、のべ1000人以上を担当してきたノウハウをお伝えします
清風南海中学校ってどんな学校?
清風南海中学校の…
- 所在地
- 進学実績
- コース
- 入試日程・入試方式
- 偏差値
- 併願パターン
- おすすめ塾
になどついては、『【清風南海中学校】進学実績・入試日程・偏差値・おすすめの塾は?』という記事にくわしくまとめました。
気になるかたは、ぜひそちらの記事もご覧くださいね↓
清風南海中学校の社会はどんな問題?
それでは、清風南海中学校<2020年度A入試>社会の入試問題では、どんな問題が出題されたのかを見ていきましょう!
【時間】
40分
【満点】
80点
【構成】
- 地理 10問
- 歴史 5問
- 歴史 5問
- 公民・時事 5問
- 公民 5問
【特徴】
2019年度A入試の問題は、大問4題でしたが、2020年度A入試では、大問5題となりました。
合計の小問数も、30問で変化はありませんでした。
1.計算問題が出題される
清風南海中学校の社会の入試の問題では、よく計算問題が出題されます。
2020年度A入試では、清風南海中学校と北極との、おおよその距離を求めさせる計算問題が出題されました。
ただ、その前段階として、清風南海中学校の対せき点(地球の真裏側の地点)の、緯度・経度を求めさせる問題が出されています。
「緯度・経度とはどういう数字か?」を、きちんと理解していないと、計算問題まで行きつけません。

うまく作られていますね…
年度によっては、人口密度を計算させたり、資料問題に計算をおりまぜたりする場合があります。
2.表・グラフなどの資料問題が出題される
雨温図を見て、気候・場所を答える問題がよく出題されています。
2020年度のA入試の問題では、兵庫県北部・大阪府・和歌山県南部の雨温図が出題されました。
それぞれの気候をきちんと理解できているかを問う、スタンダードな問題です。
地理ではその他に、製造品出荷額の円グラフ、貿易港の輸入額・輸入品目の表、乳用牛・肉用牛の飼育頭数の都道府県ランキングなども出題されました。
歴史では、日本の「元号」の一覧(一部)が出たのが、特徴的でした。
また、葛飾北斎、歌川広重、尾形光琳の絵を答える問題も出題されています。
3.内容正誤問題が出題される
例えば、次のような内容正誤の問題が数問出題されます。
「文永」の年号が用いられていた時におこった出来事について述べた次のⅠ・Ⅱの文の正誤を判断し、その組み合わせとして正しいものを、右のア~エのうちから1つ選び、記号で答えなさい。
Ⅰ 元軍が高麗軍を従えて、日本に攻め寄せた。
清風南海中学校2020年度A入試社会より引用
Ⅱ 後醍醐天皇を中心とした新たな体制で政治が行われた。
この問題の場合は「文永」と見て、「文永の役」、つまり、元寇だと読みかえる必要がありますね。
また、非常に細かい部分の制度が問われるときもあります。
4.時代のならびかえ問題が出題される
内容正誤問題に並んでやっかいなのが、時代のならびかえ問題です。
一般的には、例えば…
奈良時代の内容 → 平安時代の内容 → 鎌倉時代の内容
というように、別の時代の内容をならびかえさせる「ならびかえ問題」がよく出題されます。
でも、清風南海中学校では、1つの時代の中で、年代が近い細かい「ならびかえ問題」が出題されます。
こちらも苦手にしている受験生が多いでしょう。
【対策】

それでは、対策の方法を見ていきましょう
1.計算問題が出題される
清風南海レベルを受験する生徒の場合、基本的な計算力は問題ないはずです。
計算力よりも、与えられた数字をどのように使って答えを導くかという読解力が必要です。
社会の計算問題の定番は、時差や地図の縮尺に関する問題です。
あまり類題はありませんので、清風南海中学校の過去問を使って、トレーニングしておくことが大切です。
また、すぐに解き方が思いつかない場合には、いったん後回しにしたほうがいいでしょう。
2.表・グラフなどの資料問題が出題される
2020年度A入試の問題では、「元号」一覧が出題されました。
「元号」の表を見て、圧倒された受験生もいたかもしれません。
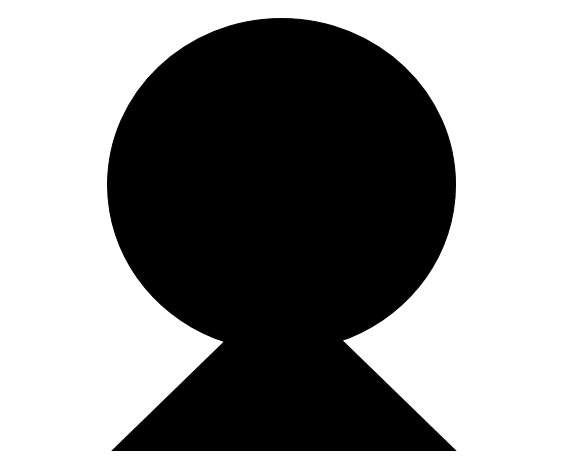
えー!
こんな元号、塾で習ってないし!
でも、落ち着いて問題文を読んでみると、きちんとヒントが隠されています。
表・グラフの問題も、基本的には知識で解くことができます。
ですので、まずはテキストの基本知識をインプットしておくことが先決ですね。
ただ、知識で解くのではなく、表・グラフの内容を「読み解く」問題では、文字通り「読解力」が要求されます。
選択肢をていねいに読み、表・グラフに示されている内容と合っているか、ていねいにチェックしなければなりません。

社会やのに、求められているのは国語力やん
また、表・グラフなどの資料問題に、計算が必要な場合もあります。
焦らずに、落ち着いて計算しましょう。
地形図の問題では、地図上から地図記号を探したり、等高線の数を数えたり、縮尺計算をしたりする必要があります。
時間かかりますよね(汗)
ですので、地形図の問題は、いったん後回しにしておくのがオススメです。
3.内容正誤の問題が出題される
表・グラフの資料問題と同じように、内容正誤の問題もまずは基本知識をインプットしておくのが大前提です。
ただ、中には基本レベルの知識では、対応できないような細かい正誤問題も出題されます。
資料集のすみっこに書かれているような知識です…
そのような正誤問題は、「まちがっても仕方がない」と、いったん割り切ってしまいましょう。
難しいのは、他の受験生にとっても同じ!
まちがったとしても、あまり差の出ない問題かもしれません。
中学校側も、高得点を阻止するために作った難問の可能性もあります。
4.時代のならびかえ問題が出題される
清風南海中学校の「時代のならびかえ問題」は、近い年代で細かいならびかえが出題されることがあります。
1番手っ取り早いのは、語呂合わせなどで、年代を丸暗記をしておくことです。
ただし、年代の語呂合わせ暗記は、効率が悪い…
年代を暗記するために、語呂を暗記する…
暗記のための暗記ですから…
ですので、語呂合わせによる年代の丸暗記は、あまりオススメしていません。
時代の流れを変えるようなできごとの年、有名なできごとが起こった年は、もちろん覚えておいたほうがいいでしょう。

例えば、明治時代が1868年スタートだとか、終戦が1945年だとか
問題を解いていくなかで、よく登場するできごとの年は、自然と覚えていくものです。
何度も出会うなかで、自然と記憶にすりこんでいくのが、暗記のコツでもあります!
そして、歴史を学ぶ上で意識しておくといいのが、「歴史の流れ」つまり、ストーリーです。
「歴史の流れ」をストーリーとして理解することで、「時代のならびかえ問題」をストーリー展開で解くことができます。
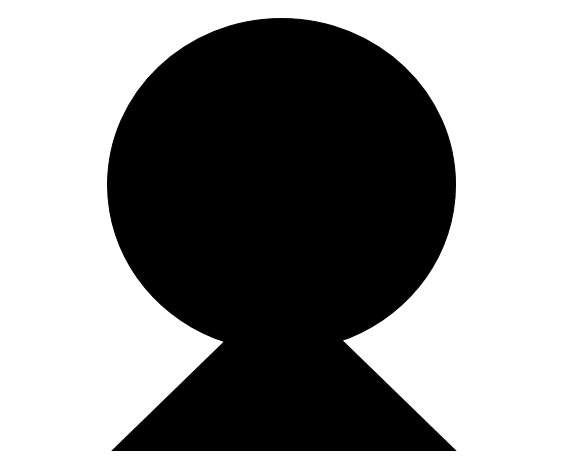
サンフランシスコ平和条約でみんなと仲直りして、その後、ソ連とは個別に仲直り。
で、国際連合に加盟できたんだ
というように、流れを押さえておくことで、1951年とか1956年といった数字を覚えていなくても、「時代のならびかえ問題」を解きやすくなります。
また、「歴史の流れ」を意識して学習することで、記憶しやすく、また、忘れにくくなるという効果も、もちろんありますね。
【プロ家庭教師から一言】
正しいものを選ばせる記号問題だけでなく、「誤っているもの」を選ばせる記号選択問題がよく出題されます。
設問をきちんと読んで、うっかり読み飛ばさないように気を付けましょう。