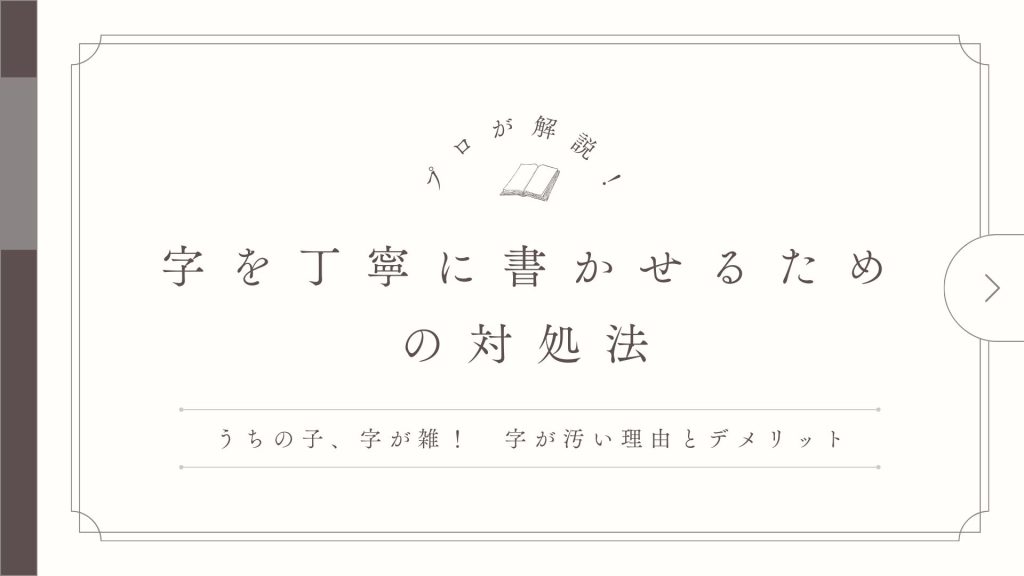
こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。

うちの子、字がめっちゃ雑…
注意しても聞かないけど、どうしたらいいの?
そのようにお悩みのお母様・お父様も多いのではないでしょうか?
今回の記事では…
- 汚い字を書く5つの理由
- 雑な字を書いてしまうデメリット5つ
- 読めない字は治るのか?
- 字が雑な子へのプロ家庭教師の対応方法
- ていねいな字を書くための6つのトーク(アドバイス)
がわかります。
字が雑だと、ふだんの生活からテストの結果まで、いろいろ困ることが出てきます…
でも、子どもたち自身は気にしている様子もなく、直す気もない…
字が汚い原因から解決方法まで、プロ講師が持論を語ります!

元塾講師・プロ家庭教師として、のべ1000人以上を担当してきたノウハウをお伝えします
子どもたちが雑な字を書く5つの理由

まず、どうして子どもたちが雑な字を書いてしまうのか、その原因を探っておきましょう。
子どもたちが読めない字を書いてしまう理由は…
- めんどうくさがり
- 頭の回転が速い
- 時間がなくて急いでいる
- 筆記用具や机など環境・道具が整っていない
- 字の形を認識したり、落ち着いて字を書くのが苦手
という5つが多いでしょう。
掘り下げて見ていきましょう。
めんどうくさがり
基本的に字が雑な子は、性格的に「めんどうくさがり」さんが多いですよね。
本当は、ていねいな字を書こうと思えば書けます。
でも、字をきれいに書こうとする気は特になし!という子は多いでしょう。

オレ、そのタイプやわ
頭の回転が速い
中には、頭の回転が速い子で、字が雑な子もけっこういます。
最難関の中学・高校・大学に合格するような子です。
頭の回転が速いので、手を動かして書くスピードが追いつきません。

オレ、そのタイプやわ。
って言ってみたいわ
ただ、頭の回転が速いので、字が汚いことを正当化してしまいがちです。
「自分は読めるから大丈夫」とか「本番はていねいに書ける」など、いろいろな言い訳をしますよね…
本当に賢い子は、字が雑でもまちがえないですし、入試本番はていねいに書けるので大丈夫です。
ただ、ほとんどのお子様の場合、自分で字を読み間違えたり、テストでも字が雑で損をしているのが現実です。
時間がなくて急いでいる
塾講師・予備校講師の板書スピードが速く、ていねいにノートを書いている時間がないという子もいます。
黒板(ホワイトボード)の文字が、書いては消されていくので、ただただノートを写すだけになりがちです…
急いでいるとき以外はていねいに書けるなら問題ないでしょう。
筆記用具や机など環境・道具が整っていない
中には、「環境が整っていない」ことで、字がていねいに書けない子もいます。
たとえば…
- えんぴつの持ち方が安定せず筆圧が弱い
- 机といすの高さが合っていない
- 姿勢が悪い
- 方眼ノートを使わずにひっ算が斜めになる
などですね。
えんぴつの持ち方を変えるだけで、しっかりとした字になる子もいます。
また、キャスター付きに椅子だと、姿勢が定まらない子は多いですよ。
マス目(方眼)ノートを使うことで、ていねいな文字・数字を書ける子もいるでしょう。

子どもたち本人では気づけないこともあります
また、タブレット端末の扱いにも注意が必要だと私は考えています。
おとなの場合には、字を書く感覚ができあがっているので問題ありませんが、まだ字を書く感覚ができ上っていない子どもたちには、タブレットと紙での学習とでは、大きな違いがあります。
えんぴつで紙に書くからこそ、適度な筆圧を体を覚えられます。
文章を紙に書くことによって、自分の考えをまとめることもできます。
タブレット学習が、子どもたちから字を書く機会を奪っていないか、考え直してみる必要はありそうですね。
字の形を認識したり、落ち着いて字を書くのが苦手
字をていねいに書こうとしても、書けない子もいます。
その場合、「字をきれいに書きなさい」と注意しても、本人としてはどうしようもありません。
努力や意識の問題ではなく、文字の形を認識することや、注意深く文字を書くことが不得手なんです。

私が担当するお子様でも、一定数いらっしゃいます
読字障害・ADHD(注意欠陥・多動症)などの発達障害が関わっていることが多いでしょう。
ただ、学校の先生や塾講師などは、ご家庭に気を遣って「発達障害」といったワードを言わないこともあります。
素人が判断するのは難しいので、専門の医療機関に相談・受診することが大切です↓
読めない字を書くデメリット5つ

次に、汚い字を書くことで、どんなデメリットがあるのかも見ておきましょう。
字が雑であるデメリットは…
- 第一印象がよくない
- 相手に正しく伝わらない
- テストで不正解とみなされる
- 自分の字でだまされる
- 注意されてモチベーションが下がる
の5つです。
1つずつ見ていきましょう。
第一印象がよくない
初めて会う人や、顔や性格がわからない相手に、文字で自分をアピールしないといけないときがあります。
たとえば、履歴書や答案用紙、手紙などですね。
そのときに、字がていねいな書類、字が雑な文書類とでは、どちらの人物を信頼しようと思うでしょうか?
第一印象がいいのは、やはり字がていねいな人ですよね。

逆に字が雑だと、第一印象はよくないですね…
相手に正しく伝わらない
第一印象だけでなく、自分が考えていることが、相手に正しく伝わりません。
子どもだけでなく、おとなでも字が雑な人がいますよね…
最近はパソコンやスマホで文字を入力することが増えてはいますが、字が雑ない人といっしょに仕事をすると、メモが読めずに苦労することが多いでしょう。

今、だれの顔が思い浮かびました?
字が雑だと、他の人に迷惑をかけてしまうことがあります。
また、自分のメッセージが相手に伝わらず、自分が損をすることもあるでしょう。
テストで不正解とみなされる
子どもの場合、実生活よりも、勉強面で損をしていることが多いはずです。
- 「シ」と「ツ」
- 「ン」と「ソ」
- 「や」と「か」
- 「り」と「い」
- 「う」と「ら」
など、本人は正しく書いているつもりでも、丸つけ・採点する側からすれば、判別できないときがあります。
小学校の先生など、その子のことをよく理解してくれている人なら、正解にしてもらえるかもしれません。
ただ、知らない採点官が丸つけしたり、機械で読み取ったりする場合には、不正解としてはじかれる可能性が高くなります。
自己採点よりも点数が低く出る場合は要注意です。
自分の字でだまされる
算数・数学では、自分の字が汚くて、自分で読み間違える子も多いです。
- 「0」と「6」
- 「7」と「9」
- 「2」と「3」
など、数字がつぶれてしまい、書いた本人でも読み取れず計算ミスにつながるという事態におちいりがちです。
また、ひっ算が斜めになり、ケタがずれてしまう子もたくさんいます。

自分の字で損をしてることに気付いてほしいやんな
注意されてモチベーションが下がる
「字が汚い」と、何度も注意されることで、勉強へのモチベーションが下がってしまいます。
子どもたちとしては…
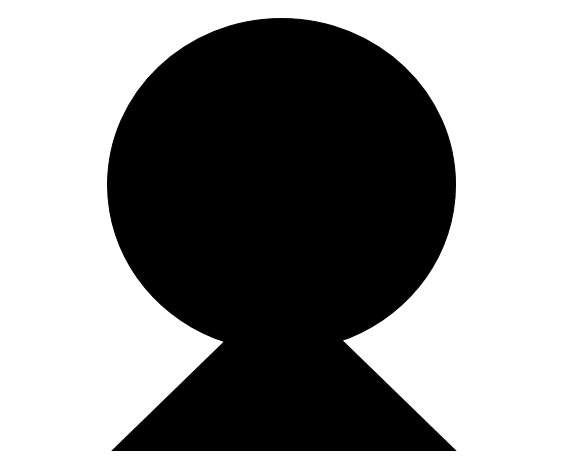
きちんと勉強してるんだから、字くらいで怒られたくない!
と考えている子がほとんどでしょう。
親子で不毛な言い争いになることも多いですよね…
雑な字は直せるの?
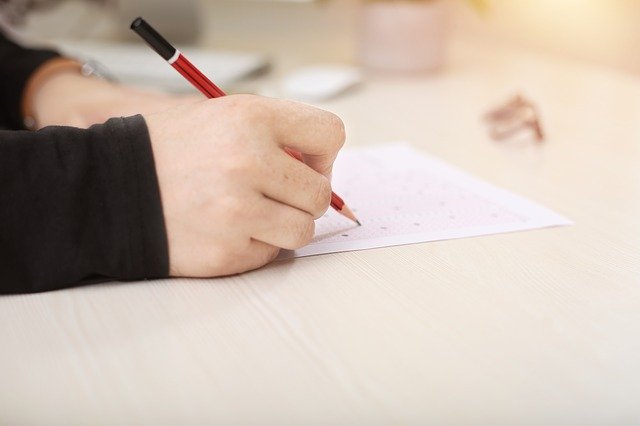
いよいよ本題に入りますが、汚い字を書く子に、ていねいな字を書かせることはできるのでしょうか?
まず、文字の形を認識できなかったり、落ち着いて文字を書けない子は、さきほどお伝えした通り別です。
本人の努力や意識とは別問題ですから、専門の医療機関に相談することが大切です。

くれぐれもネットの情報などで判断しないようにしましょう
一方、ていねいに字を書こうと思えば書けるのに、雑な字を書く子は果たして字がきれいに書けるのか、をこの章ではお話します。
結論を言うと…
- すぐに変わる子もいる
- なかなか変わらない子もいる
です。
おそらくお母様・お父様も、字をていねいに書くようお子様を説得したはずです。
私たちプロ講師が子どもたちを説得する場合も、(情けない話ですが)結果は同じようなものです…
中には、字をていねいに書くようにすぐに意識し始める子もいます。
でも、たいていの子は、ていねいな字をすぐに書くようにはなりません。
無意識で長いあいだ雑な字を書いているので、急に変えようとしても変えられないでしょう。

自分のクセってなかなか治らへんやん
字が雑な子へのプロ家庭教師の対処法

読めない字を書く子たちに、私が対応しているのかを紹介しておきますね。
字が雑な子への私の対処法は…
受験生以外は放置
です。
「無責任だ!」と思われるかもしれません。
でも、そのかわりに…
ていねいに書かないと不正解になる
ということははっきりと伝え、読めない字は容赦なくバツ、不正解にします。
子どもたちはもちろん抗議します。
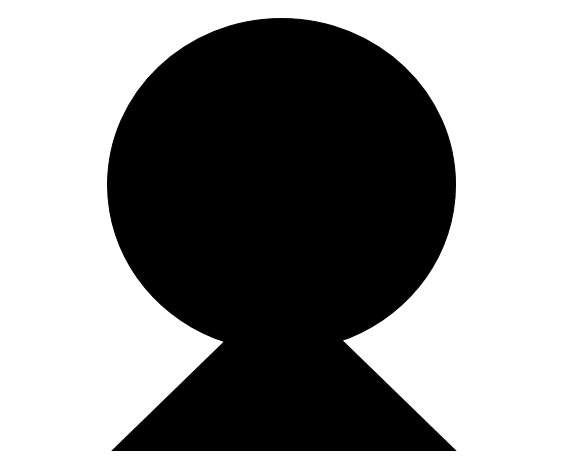
「ア」のつもりで書いてん!
「イ」ちゃうで!
これくらいいいやん!
私はさらっとこう言うだけです。

〇か×を決めるのは、採点する側な。
残念!
これで終わり。
字が汚いことをネチネチくどくどと責めても、関係がこじれるだけです。
読めない字は容赦なくバツにして、次に進みます。
受験生以外には、気持ちよく楽しく勉強に取り組んでもらうことを優先します。
なぜ私がこんな態度を取っているかというと…
字が雑なことで損をしていることに気づいてもらう
ことが必要だからです。
そして、本人の意識が変わるのを待つのが私の基本方針です。
本人がていねいに書くと決めたときに、ていねいに書くようになるものです。

なんだ…特効薬はないのか…
プロ講師のくせにがっかり…
と思われても仕方がありませんね。
ただ、受験生に対しては、さらに踏み込んで、ていねいに書くためのトークをします。
次の章では、ていねいな文字をかくための6つの話を紹介します。
ていねいな字を書くための6つのトーク(アドバイス)
私が受験生に話す、ていねいな字を書くためのトークを紹介しますね。
ていねいに書くよう意識づけるための話は…
- 文字は何のために発明されたのか?
- 入試は落とすためのテストである
- 答案用紙はラブレター
- 丸つけ・採点する人の気持ちは?
- 受験・人生で損(得)をした実話
- 君なら入試までに変えられる
の6つです。
1つ1つ見ていきましょう。
文字は何のために発明されたのか?
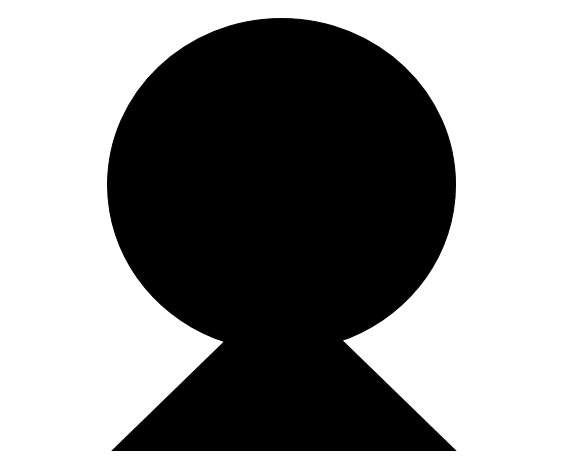
自分が読めるから、雑でもいいやん
という屁理屈を言う子って、必ずいますよね。
そういう屁理屈くんには、「文字は何のために発明されたのか?」という話をします。
文字は発明されたのは…
- あとで自分が読んで思い出すため
- 他の人に自分のメッセージを伝えるため
です。
文字が発明される前は、自分のアイディアを形として書き残すことができませんでした。
文字が発明されることによって、私たちは先人の知恵を読んで知ることができます。
私たちの生活が進歩し成り立っているのは、文字のおかげですよね。

たいていの問題は、先人が本に答えを出してくれてるやん
ですので、屁理屈くんの言う「自分さえ読めたらいい」というのは、半分正解で半分はまちがいです。
屁理屈くんが気づかないだけで、周りの人は実は迷惑しているかもしれません。
ていねいに書けるのに書かないのは、独りよがりで想像力に欠けています。
ということを、気づいてもらいます。
入試は落とすためのテストである
入試というテストの性質を話すこともあります。
入学試験をかんたんにしてしまうと、差がつかなくなってしまいます。
問題の作成者や採点官は、合格者と不合格者の差をつけたいんです。
つまり…
入試=受験生をふるいにかける装置
ですね。
雑で判別できない字を、学校側としては正解にするわけにはいきません。
たとえば、「ア」か「イ」か判別つかない答案の場合、不正解になります。
判別できないのに正解にしてしまうと、正々堂々ていねいに書いた子たちに示しがつかないですよね。
ですので…
- 入試はスキを見せたらバツにされる
- 判読できない字=不正解
であることを、しっかりと伝えるようにしています。
答案用紙はラブレター
まだ会ったことがない2人から、ラブレターをもらいました。
2人とも顔も見たことがないですし、性格もわかりません。
好きです
付き合ってください♡
という文面も同じです。
でも、1人はとてもきれいな字で、一方は、めちゃくちゃ汚い字で読むのに苦労します。
- Aさん:字がていねいは人
- Bさん:読むのに苦労する人
どちらの手紙に誠意を感じますか?
そりゃ、Aさんに良い印象を持ちますよね。

屁理屈くんは、Bさんと言いますが(笑)
さきほどお伝えした通り、字がていねいだと、第一印象が良いですよね。
答案用紙でも同じです。
採点官は、受験生の顔や性格を知りません。
文字でしかその子を判断して、合否を決めることしかできないのです。
字がていねいな子と雑な子が、暫定で同点で、どちらかしか入学させられないとします。
どちらを合格させ、どちらを不合格にするでしょうか?
「合格したい!入学したい!」という気持ちが伝わってくるのは、字がていねいに書けている子でしょう。
さきほどのトークでお伝えした通り、スキを見せた方が不合格、つまり、字が雑な方がふるいにかけて落とされる可能性大ですよね。
丸つけ・採点する人の気持ちは?
丸つけ・採点する側の立場を考えさるようなトークもします。
入学試験の採点官は、何人分の答案用紙に目を通すでしょうか?
何百人、多ければ、何千人という受験生の答案を採点しなければなりません。
ただでさえ、作文・小論文や英作文、記述答案を採点するのは、とても神経を使います。

私は経験があるので、その苦労話がしやすいです
そんな中、判読できない汚い字の答案が現れたら、採点者はどんな気持ちになるでしょうか?
正直なところ、腹が立ちます。
具体的には…
- 読みたくない(0点にしたい)
- 減点したい
という気持ちにさせられます。
採点する学校の先生も、人間ですからね。
一方、字がていねいだと、好印象の状態で丸つけしてもらえます。
視力が悪いおじいちゃん先生が、読めない字をことごとくバツ(不正解)にしたという都市伝説もありますよね(笑)
受験・人生で損(得)をした話
私は字や絵をかくのが得意な方なので、私の授業を見学してくださったお母様・お父様には信用してもらいやすいと自負しています。
私は塾講師でありながら、実はおしゃべりがあまり上手ではありません。
ですので、字や絵のていねいさで、ずいぶん得をしています。
そのような字がていねいで得をしたリアルな話や、字が雑で損をした実話を話してあげてみてください。

授業から脇にそれた雑談って、子どもたち好きですよね
どちらかと言えば、字が汚くて損をした話をしてあげるといいでしょう。
字がていねいで得をした話だと、子どもにとっては自慢話ととらえらえ、聞く耳を持ってもらえないかもしれません。
お母様・お父様自身の体験談でなくても、知り合いの話でも構いません。

お母さんの同僚のAさん、字が汚くて、取引先に誤解されて、上司に怒られていたわ
とかでOKです。
勉強のときに話すと、子どもにはイヤミに聞こえるかもしれません。
ふだんの何気ない会話で話してあげるのもいいですね。
私は、匿名でこんなストーリーを話します。
ある学校に合格できる力のある子がいてん。
学校が主催するプレテストを余裕のつもりで受けて、自己採点でも大丈夫やってん。
でも、フタを開けてみたら、E判定。
そのあと開催された学校の説明会で、先生に聞いてみたら、「崩れた字はバツにしたからかも」と言われたらしいわ。
それ以来、その子は字をていねいに書くようになって、無事合格したわ。
子どもたちには、どんな話が刺さるのか、わかりません。
手を変え品を変え、いろいろな話をしてみる必要はあります。
君なら入試までに変えられる
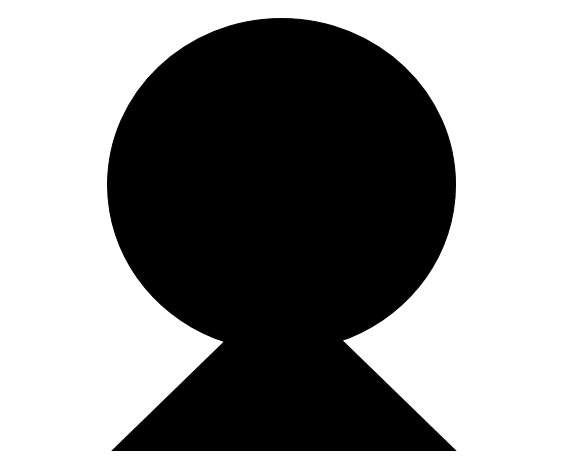
入試本番には、ていねいに書くから大丈夫
という子も、けっこういますよね。
もちろんその子の言うことを信じてあげたいものです。
でも…
- 練習でできないことは本番でもできない
- 本番でしないことを練習ですべきでない
ですよね。
そのことをきちんと話したうえで、入試本番にいきなり字を変えることはできないので、期限を決めるようにしています。
たとえば…
- 中学受験:プレテスト
- 高校受験:実力テスト・模試
- 大学受験:総合型・推薦型選抜
などが、2学期から山場を迎えます。
また、受験校の過去問を解き始めるのも、2学期であることが多いでしょう。
ですので「2学期からは字をていねいに書こう!」と、タイムリミットを決めるわけです。

山田くん(仮名)なら、「約束」を守って、ていねいに書けるよな
と、その子のことを信じます。
ふだんとは違った真剣な表情・口調で言うのも効果的です。
また、宿題をしなかったり、答えを丸写ししたり、「約束を破る」ことに対して、私は厳しく接しています。
ですので、「約束」という言葉は特に強調するようにしています。
お子様やお母様・お父様との信頼関係がしっかりとできている場合には…

もし、2学期になっても、字がていねいに書けないと、それはただの「アホ」やからな
とクギをさすこともあります。
どんな言い方であれ、その子のことを信じていると伝えるときには、「あ、先生、本気で言ってるな」と伝わることが大切だと思っています。
まとめ:字が雑な理由とデメリット、ていねいに書かせるための対処法
今回の記事では、字が雑になる理由から、字をていねいに書かせるためのトークまでお伝えしてきました。
すぐに変えられる子はすぐに変えられます。
でも、変えられない子は、なかなか変えられません。
かなり根気が必要で、時間もかかりますが、字をていねいに書くことが、自分のためでもあるのだと気づいてもらうことが大切ですね。
特効薬はなかなかないかもしれませんが、お母様・お父様の参考になれば幸いです!



