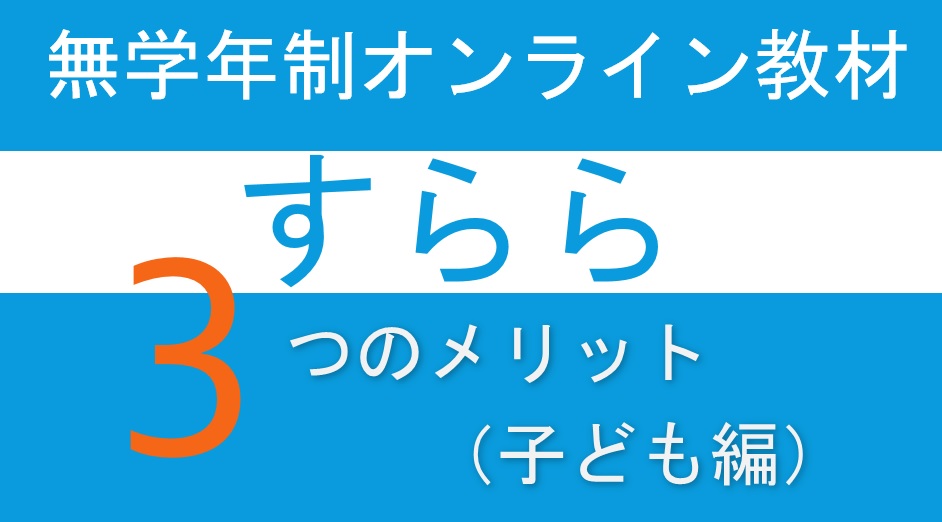こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。
プロ家庭教師へのご依頼として、受験指導はもちろん多いのですが、発達障害のお子様をお持ちのお母様・お父様からのご依頼も少なくありません。
特に最近、多く感じられるのが…
ADHD(注意欠陥多動性障害)
のお子様です。

うちの子に、いい勉強方法はないかな?
ADHDでも使いやすい教材はないかしら…
そのようにお悩みのお母様・お父様も多いのではないでしょうか?
今回の記事では…
- ADHDへの対処法の1つとして無学年制オンライン教材「すらら」
をご紹介します。
ADHD(注意欠陥多動性障害)とは?

最近よく知られるようになってきた「ADHD(注意欠陥多動性障害)」とは、どのようなものなのでしょうか?
(よくご存知のお母様・お父様は読み飛ばしてくださいね)
「ADHD(注意欠陥多動性障害)」は、「発達障害」の1つだとされています。
厚生労働省のホームページには、次のように書かれています。
発達障害は、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。そのため、養育者が育児の悩みを抱えたり、子どもが生きづらさを感じたりすることもあります。(中略)
厚生労働省ホームページ「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス」より引用
発達障害には、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症(学習障害)、チック症、吃音などが含まれます。
これらは、生まれつき脳の働き方に違いがあるという点が共通しています。同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を併せ持ったりすることもあります。
つまり、本来は生まれつき脳の働きかたが違っているだけなのですが、違っているがゆえに、「生きづらさ」を感じてしまうということですね。
さらに、「ADHD(注意欠陥多動性障害)」の特徴としては、次のように説明されています。
発達年齢に比べて、落ち着きがない、待てない(多動性-衝動性)、注意が持続しにくい、作業にミスが多い(不注意)といった特性があります。多動性−衝動性と不注意の両方が認められる場合も、いずれか一方が認められる場合もあります。
厚生労働省ホームページ「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス」より引用

少し成長が遅い気がする…
もしかしたら発達障害なんじゃないか…
何が良くなかったんだろうか…
きっとお母様・お父様は、お子様のことを思い、悩んだり、ご自分を責めたりしたこともあるのではないでしょうか…
また、これまで「発達障害」や「ADHD(注意欠陥多動性障害)」といった定義がなく、研究がされていなかった時代には、そうとは気づかれずに、もっと苦しい思いをされたかたも多かったのだろうと思われます。
最近では、子どもだけでなく、「大人の発達障害」も注目されていますね。
厚生労働省のホームページには、次のようにも書かれています。
発達障害があっても、本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や学校・職場での過ごし方を工夫することで、持っている力を活かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができます。
厚生労働省ホームページ「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス」より引用
まず、専門家に相談し、診断してもらうのがいいでしょう。
ただ、相談・診断に行くかどうか悩まれるかたが多いと、よく聞きます。
自分、もしくは、わが子が、「発達障害と診断されるかもしれない」と考えるのはつらいです。
「国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター」というサイトでは、日本全国の相談窓口を紹介しています。
参考にしていただければ幸いです。
勉強面で「ADHD(注意欠陥多動性障害)」とどう向き合うか

日常生活のいろいろな面で工夫が必要となりますが、勉強面においては、どのように「ADHD(注意欠陥多動性障害)」と向き合っていけばいいのでしょうか?
さきほどご紹介した通り、ADHD(注意欠陥多動性障害)のかたは…
- 落ち着きがない
- 待てない
- 注意が持続しにくい
- 作業にミスが多い
といった特徴が見られます。
ですので、学校生活の中で…
- 先生の話を集中して聞けない
- 授業注意しゃべったり立ち歩いたりしてしまう
といった状態に悩んでしまうことが多いようです。
学校生活や塾の授業では集中力が保てないため、私のような家庭教師にご依頼されるご家庭もあります。
以前担当していた小学生の男の子も、「ADHD(注意欠陥多動性障害)」と診断されていました。
実際に私が彼のとなりで指導していても、急に視線が固まってしまうことがよくありました。
文章を読んでいるようで読んでいない、何か別のことを考えてしまっているようでした。

今、どこ読んでる?
などと声をかけて、注意をテキストに引き戻してあげなければなりません。
また、別の中学生の男の子は、お母様が専門家に相談しようか悩んでいました。
いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる状態です。
その子も、急に集中力が途切れてしまったり、私が書いたノートを正確に写すことができなかったりしました。
また、入試前で勉強しなければならないときでも、ゲームをしたい衝動を抑えられないようでした。
でも、本人は専門家に相談しにいくのを拒んでいました。
「俺は、障害じゃない!」と。
生徒本人もお母様もそれぞれが、どう向き合えばいいのかという葛藤で苦しんでいました。
このように、ADHD(注意欠陥多動性障害)をお持ちの子どもたちは、勉強するときにサポートが必要になることがあります。
【ADHDのお子様に】無学年制オンライン教材「すらら」の可能性
ただ、ADHD(注意欠陥多動性障害)に理解のある塾を探すのは、なかなかむずかしいでしょう。
また、プロ家庭教師の場合は、1時間で1万円前後の指導料になることが多く、経済的な負担も多くなってしまいます。
私自身も京阪神地区からご依頼をいただいた場合には、ご家庭にうかがうことができますが、全国にうかがうことはできません。

スケジュール上、お引き受けできる時間にも限界があります…
申し訳ありません…
そこで、この記事では、無学年制オンライン教材「すらら」をご紹介します。
無学年方式インターネット学習教材「すらら」は、タブレットやパソコンを使って学習する通信教材です。
他の通信教材と大きく異なるところは、「無学年方式」であるところです。
多くの通信教材では、「5月には5月のカリキュラムに合わせた教材を配送」という形で、カリキュラムに合わせた学習が基本となります。
一方、「無学年方式」の「すらら」では、オンライン上に全単元がそろっているので、自分にとって必要な単元を、自分にとって必要な時期に学習することができます。
また、「すらら」の利用料金は、1万円未満の定額制(税抜き)ですです。
クラス指導塾や個別指導塾に通ったり、家庭教師に依頼したりすると、費用が高くなってしまううえに、学習する時間が固定されたり、限られてしまいます。
しかも、インターネット環境が整っていれば、使い放題です。
「すらら」がADHDのお子様におすすめなわけ
では、なぜ無学年制オンライン教材「すらら」が、ADHDのお子様におすすめなのでしょうか?
「すらら」にはこんな特徴もあります。
- かわいいキャラクターによるレクチャー
- 1つのレクチャーが平均15分程度でスモールステップ
- 習慣化させやすいゲーミフィケーション
1つずつもう少しくわしく見ていきましょう。
かわいいキャラクターによるレクチャー
どうしても授業は、先生(大人)が子どもに教えるという形式になってしまいます。
また、勉強というと、教科書を読んだり、問題集を解いたりすることが中心になります。
でも、ADHDのお子様の中には、その形が合わない子もいらっしゃいます。
「すらら」では、かわいいキャラクターがアニメーションで授業を進めてくれます。
また、通信教材では、一方通行なレクチャーになりがちですが、「すらら」ではキャラクターが問いかけをしてくれます。
つまり、インタラクティブ(双方向)の授業を意識して、レクチャーが作られています。

プロの声優さんが、キャラクターの声を担当しているそうです
先生の話を聞くのが苦手、教科書や問題集に集中して取り組めないというお子様には、「すらら」のレクチャーが合っている可能性があります。
さきほどご紹介した、私が担当した中学生の生徒さんも、学校の先生の話を聞いたり、問題集を解いたりするのは苦手ですが、ゲームなら何時間も集中して取り組めます。
別の小学生のお子様も、学校の勉強では集中力がもたないのに、プログラミングスクールでは黙々と集中して課題に取り組んだそうです。
1つのレクチャーが平均15分程度でスモールステップ
また、「すらら」は1つのレクチャーが平均15分程度に区切られているので、集中力を持たせやすくなっています。
そもそも学校や塾の授業が50分・60分・80分などというのは、ADHDのお子様でなくても長すぎます。

人間の集中力の限界は、15分だという説もあるほど
机の前に座って、何時間も先生の話を聞く、教科書を読み、問題集を解くというのは、実はかなりの集中力を要する作業なのです。
すると、「勉強=しんどい」というイメージがついてしまい、勉強の習慣がなかなかつかなくなってしまいます。
一方、「すらら」は1つのレクチャーが平均15分で作られているので、「勉強=しんどい」というイメージがつく前に勉強し終えることができます。
レクチャーを短くするために、1つの単元を10から15に細かく区切ってレクチャー動画が作られています。
「スモールステップ」を意識して、教材が作られているので、勉強が苦手なお子様でも、一歩一歩前に進んで行くことが可能です。

「スモールステップ」は、私の指導でも大切にしています
習慣化させやすいゲーミフィケーション
「勉強=しんどい」というレッテルを貼らせないための方法として、「すらら」では、「ゲーミフィケーション」を取り入れています。
「ゲーミフィケーション」とは…
ゲーミフィケーションとはゲームデザイン要素やゲームの原則を他の分野に応用し、ユーザーのモチベーションを高め、行動を活発化させる手法を指します。ゲームとは異なり行動を活発化(学習促進)させることに目的があり、すららを頑張る動機の1つとしてもらえたらと考えております。
「すらら」公式サイトより引用
つまり、ゲーム感覚でモチベーションを高めることによって、飽きない学習システムを取り入れているということです。
たとえば、「すらら」で学習すれば、ポイントがたまります。
そのポイントで自分のアバターを変更したり、マイページをカスタマイズさせたりして、楽しむことができます。
一般的なゲームで経験値がたまると、モンスターが進化進化したり、ポイントがたまると、レアなグッズが手に入ったりしますよね。
だからこそついついゲームを続けてします…

おとなでも、ポイント2倍DAYに買い物したいますよね
ポイントが目的で勉強するって大丈夫?
お母様・お父様の中には…

ポイント目的で勉強するって、動機が不純じゃない?
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、ポイントをためるために行動が強化される(すべきことをする・してはいけないことはしない)ことは、行動心理学でも認められています。
私の指導でも、シールを貼ることで…
- 宿題が習慣化する
- 高得点を目指す
というように、勉強のきっかけにしています。
おとなからすれば「シールくらいで?」と思うかもしれません。
でも、子どもにとっては、シールでもじゅうぶんにモチベーションアップにつながります。

うちの娘もシールを貼りたいがために、トイレに行くようになりました。
トイレトレーニング成功です
ゲーミフィケーションは、学習記録を付けて、学習習慣を身につける上で、とても有効です。
「ゲームなら集中して取り組める」というお子様には、「すらら」と相性がいいかもしれません。
まとめ:【ADHDのお子様に】無学年制オンライン教材「すらら」の可能性
ます、ADHD(注意欠陥多動性障害)の特徴をお伝えしました。
お母様・お父様が抱え込まずに、発達障害の専門家に相談してくださいね。
また、ADHDへの対処法の1つとして無学年方式インターネット学習教材「すらら」を紹介しました。
少しでもお母様・お父様の参考になれば幸いです。