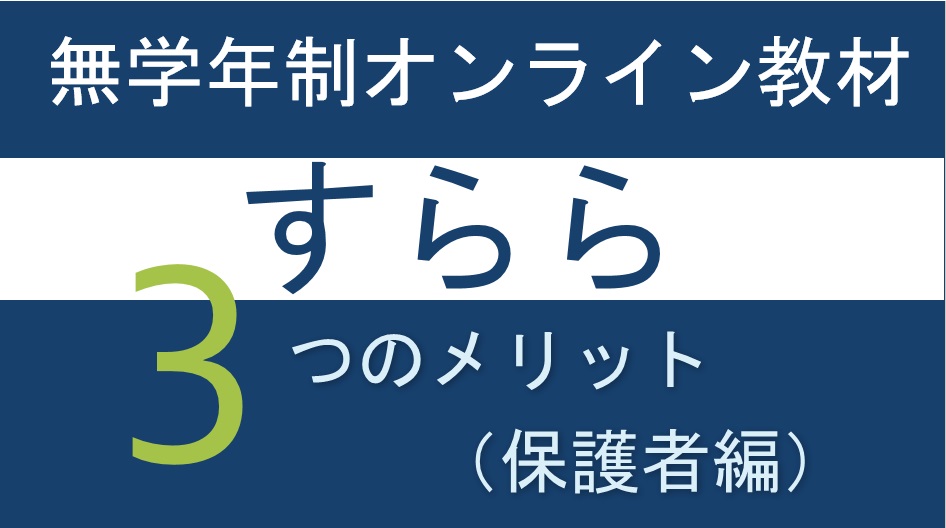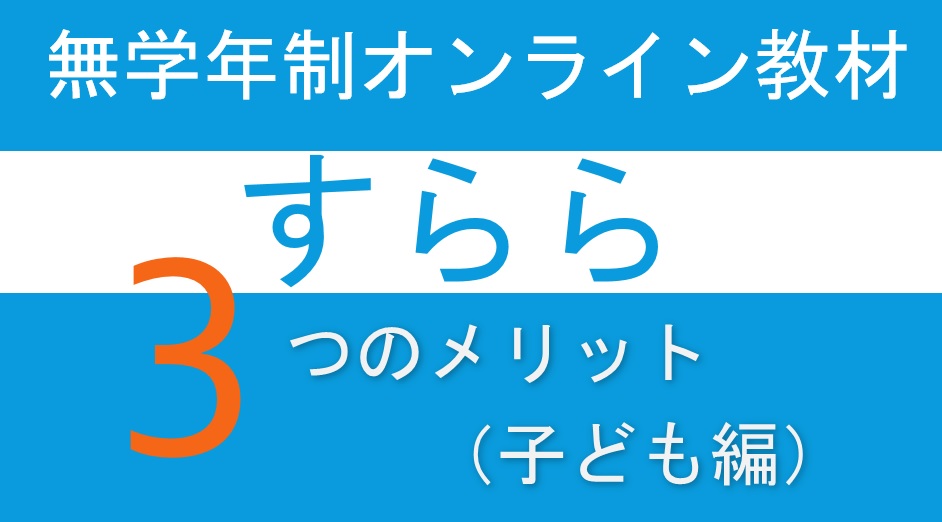
こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。

「すらら」が気になるけど、子どもにどんなメリットがあるの?
そのように悩んでいるお母様・お父様も多いのではないでしょうか?
今回の記事では…
- 無学年制オンライン教材「すらら」の子どもにとってのメリット
がわかります。
オンライン教材はたくさん登場しているので、どの教材を選べばいいのか悩みますよね。
数あるオンライン教材の中でも、「勉強に苦手な子」でも取り組みやすい「すらら」をピックアップして紹介します。

元塾講師・プロ家庭教師として、のべ1000人以上を担当したノウハウをお伝えします
無学年制オンライン教材「すらら」とは?
以前の記事でもご紹介しましたが、「すらら」は、「株式会社すららネット」が開発した、無学年制のインターネット学習教材です。
パソコンやタブレットがあれば、自宅でも学習に取り組める、eラーニング教材です。
「無学年方式」ですから、小学1年生から高校3年生の学習内容まで、復習も先取りも自由にできます。
全国約1075校の学習塾、約1096校の学校で導入されています。
(2021年3月現在)
子どもにとっての3つのメリット

では、「すらら」は、他の通信教材と違って、子どもにとってどのようなメリットがあるのでしょうか?
「すらら」の子どもにとってのメリットは…
- 苦手単元をピンポイントを復習できる
- 勉強が苦手なお子様に合わせて教材が作られている
- 学習習慣がつきやすい
の3つだと、私は考えています。
では、1つずつもう少しくわしく見ていきましょう!
苦手単元をピンポイントで復習できる
「すらら」の大きな特徴の1つが、さきほどご紹介した「無学年方式」です。
一般的な通信教材は、カリキュラムが決まっていて、そのカリキュラムに合わせて教材が送られてきます。
<従来の通信教材>
- 毎月新しい教材が送られてくる
- 定期テスト前に対策教材が送られてくる
というイメージですね。
でも、「すらら」は、インターネット上で全単元のレクチャーが配信されています。
ですので、自分の苦手に合わせて、自分のタイミングで、復習することができます。

でも、どの単元が苦手かすらわからない…
何から手を付けていいのか迷ってしまう…
そう感じるお母様・お父様もいらっしゃると思います。
「すらら」では、「つまずき診断機能」というものがあり、弱点を自動診断してくれます。
つまずき診断に沿って、「すらら」が復習内容を提案してくれるので、何をすべきかがわかります。
お子様によっては、中学生であっても、小学校内容までさかのぼって、苦手を克服しなければならない場合もありますよね。
例えば…
中学校の正負の数で通分につまずいた→小学校の分数計算にさかのぼらなければならない…
中学校の方程式で割合でつまずいた→小学校の割合に戻って復習しなければならない…
などです。
このような場合にも、「すらら」ならば、「無学年方式」なので、苦手単元をピンポイントで復習できます。
勉強が苦手なお子様に合わせて教材が作られている

勉強しなさい!
お母様・お父様はそのように言っても、勉強が苦手なお子様は勉強しようとしない…
ご家庭からよくうかがうご相談です。
では、なぜ勉強が苦手な子どもたちは、勉強しようとしないのでしょうか?
いろいろ原因はありますが、その中でも大きな原因の1つになっているのが…
教材がその子のレベルに合っていない
ということです。
子どもたち自身も勉強しなければならないことは、もちろんわかっています。
でも…
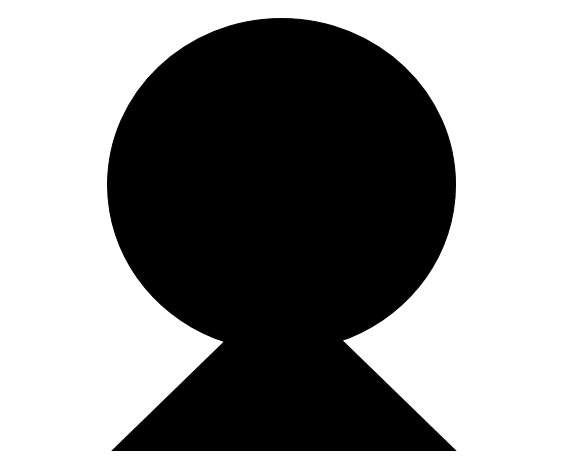
問題を解こうとしても、全然わからない…
解説を読もうとしても、意味がわからない…
中3内容が定期テストに出るけど、中1内容でつまずいている…
自分で勉強しようとしても、教材のレベルがあっていなくて、手を付けることができない子がいます。
そして、テキストや問題集、テストに対して、無力感を感じてしまっていることが多いものです。
教材が自分に合っていないのに、「教科書で独学しろ」「問題集を解け」と言われるのですから、勉強が嫌いになって当然ですよね…
一方、「すらら」は、勉強が苦手なお子様が使いやすいように開発されています。
「すらら」は下のリンク画像のように、「偏差値30台でも成績は伸びる」と、宣伝しているくらいです。
「すらら」は「スモールステップ」を意識して作られています。
1つの単元を10から15くらいに細かく分けて、レクチャーを作っています。
また、1つのレクチャーは平均15分程度でまとまっています。
ですので、勉強が苦手なお子様であっても、集中力が続きやすくなっています。

「スモールステップ」は、私が指導するときも意識しています
また、「すらら」は、先生(大人)ではなく、かわいいキャラクターがレクチャーしてくれます。
アニメーションで各単元を解説してくれるので、先生の話を聞いたり、教科書を読んだりするのが苦手なお子様でも、ハードルが低く感じられるでしょう。
通信教材というと、どうしても一方通行なレクチャーになってしまいがちです。
でも、「すらら」はキャラクターが問いかけてくれるので、インタラクティブ(双方向)な学習ができます。
このように「すらら」は…
- 見る
- 聞く
- 書く
- 読む
- 話す
という多面的な指導をしてくれるので、勉強が苦手な子どもたち向けの通信教材と言えます。
学習習慣がつきやすい
プロ家庭教師としてご家庭にうかがうと、お母様・お父様から…

ゲームばかりして、全然勉強しないんです!
というより、ゲームを取り上げて隠しても、勉強しません…
といった声がよく聞かれます。
なぜ、子どもはゲームには夢中になって、勉強には夢中になれないのでしょうか?
もちろんいろいろな理由はあるとは思いますが、何よりも…
ゲームには夢中になる仕掛けがほどこされているから
ゲームが手放せなくなってしまいます。
しかも、子どもたちに最近のゲーム事情を聞いてみると、オンラインで友達とつながったり、ログインするだけでガチャができたり…
私たち大人が子どもの頃よりも、ゲームが進化していますよね。
ますます中毒性が増していると、感じているお母様・お父様も多いのではないでしょうか?

私も、ポケモン、ファイナルファンタジー、ドラクエにどっぷりでしたが…
では、どうすれば、ゲームを手放して、勉強に向き合ってくれるのでしょうか?
答えは…
ゲームの要素を勉強に取り入れる
ということです。
ゲームの要素を別のことに取り入れて、行動へのモチベーションを上げることを「ゲーミフィケーション」と言います。
「ゲーミフィケーション」とは…
「ゲーミフィケーション」は、ツマラナイをワクワクに変えます。楽しくてハマってしまうゲーム要素を活用して、能動的に人を行動させる仕組みです。
一般社団法人日本ゲーミフィケーション協会ホームページより引用
楽しいことだと自然に人は動きますが、楽しくないことだと中々人は動いてくれません。しかし、ビジネスやプライベートでは、楽しくなくても取り組まなくてはならない状況が起こりえます。ゲーミフィケーションは、それを改善するモチベーションマネジメント手法です。そして、つまらないことを改善するだけでなく、楽しいことはより楽しくなる仕掛けを作り出します。
「ゲーミフィケーション」は身近なところで使われています。
例えば、わが家では娘のトイレトレーニングとして、トイレに行けたらシールを貼るということをしています。
娘はシールを貼りたいがために、トイレに行くようになりました。

トイレはシールだらけです
これも「トイレに行く」というモチベーションを上げるための、「ゲーミフィケーション」ですよね。
前置きが長くなりましたが、「すらら」では、「ゲーミフィケーション」を取り入れています。
「すらら」で勉強すると、ポイントを獲得できます。
そのポイントでキャラクターを育てたり、マイページをカスタマイズしたりすることができます。
また、そのマイページを、全国の「すらら」で勉強している仲間に公開することもできます。
このように…
- 勉強するとポイントがたまる
- ポイントを楽しく使える
- 自己表現で仲間とつながれる
このように、「すらら」では、「ゲーミフィケーション」を取り入れることによって、勉強の習慣をつけられるように工夫されています。
【無学年制オンライン教材すらら】子どもにとっての3つのメリット まとめ
ここまで、子どもたちにとっての「すらら」のメリットを紹介してきました。
さきほど、教材のレベルが自分に合っていることが大切だとご紹介しました。
「すらら」は、無料体験することができます。
まずは、無料体験で「すらら」との相性を確かめることが重要です。
無料体験や資料請求は、「すらら」の公式サイトからどうぞ↓