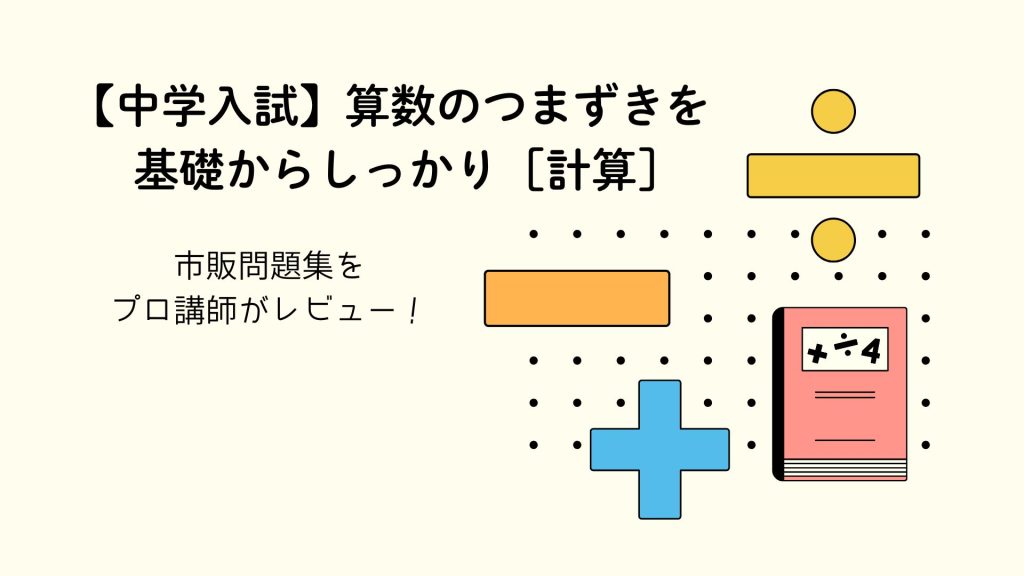
こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。

うちの子、計算が弱いかも…
おすすめの教材は何かない?
そのようにお悩みのお母様・お父様も多いのではないでしょうか。
基本的には、小学校の計算ドリルと塾の計算問題集をやりこむことをおすすめしています。
ただ…
「小学校のドリルはかんたん過ぎる…」
「中学受験塾の計算問題集がむずかし過ぎる…」
と感じているご家庭も多いものです。
私が担当するご家庭といっしょに使っているのが「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」です↓
今回の記事では…
- 「基礎からしっかり」の特徴・メリット
- どんな子におすすめか
- 「基礎からしっかり」の効果的な使い方
- 使うときの注意点
がわかります。
計算力は、算数の土台です。
まずはしっかりと計算力をつけて、計算以外のところで思考力を発揮できるようにしていきましょう!

元塾講師・現プロ家庭教師として、のべ1000人以上を担当してきたノウハウをお伝えします
【中学受験】算数では計算力がどうして大事?
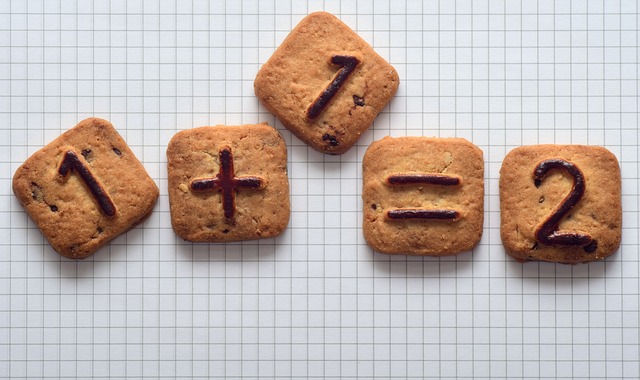
教材の紹介する前に、どうして計算力が重要なのかを再確認しておきましょう。
「計算力が大切なのは当然!」というかたは読み飛ばしてくださいね。
中学受験の算数で、計算の力が必要なのは…
- 計算でまちがったら水の泡
- 脳の容量を思考に使える
からですね。
せっかく式を作れても、計算がまちがっていたら0点です。
計算をミスしたその1問(たとえば4点)が、入試本番で合否を分けることもあり得ます。
また、中学受験の算数は、「考える力」が問われます。
脳の容量を、思考に割かなければなりません。
それなのに、計算に脳のメモリを消費してしまうのは、とても不利なんです…

計算しているうちに、何を求めるために計算していたのかわからなくなる「計算迷子」も…
どんな塾でも計算問題集を使っているのはそのためですね。
計算力は、じっくり考えるのに必須の「武器」です。
まずは計算力という「武器」を身につけて、算数に立ち向かっていきましょう。
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」ってどんな教材?
まずは特徴から見ていきましょう。
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」の特徴を一言で言うと、
中学受験算数の計算の入門編
小学校の計算ドリルくらいの内容から、中学受験に必要な基礎的な計算がまとめられています。
- 四則計算の順番
- 分数・小数の計算
- 単位
などの計算や算数の基本から、
- 等差数列
- 分配法則
- 逆算(穴埋め算・□算)
といった計算の工夫、中学受験に必要な知識も学ぶことができます。
それらを40弱のテーマに細かく分けてくれています。
また、各単元が見開きでおさまっており、
- よんでわかる【例題】
- かいてデキる【穴埋め例題】
- マスター問題【類題】
の順番で練習することができます。
「よんでわかる」は例題で、その見開きの計算テーマをくわしく解説しています。
「かいてデキる」は穴埋め形式の例題です。
「よんでわかる」で学んだことを、穴埋めをしながら、自分で再現していくように作られています。
「マスター問題」は類題で、各テーマに8問ほど用意されています。
自分で解けるかどうか、確かめることができます。

「わかる」と「できる」は別物やもんな
また、複数のテーマをまとめた「たしかめテスト」が6つほど用意されています。
いわゆる章末問題・まとめ問題で、「よんでわかる・かいてデキる・マスター問題」で学んだことを、もう一度チェックできます。
※中学受験全体のロードマップはこちらの記事をご覧ください↓
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」のメリットは?
では、メリットは何でしょうか?
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」を使うメリットは…
- 苦手な計算をピンポイントで復習できる
- 例題→穴埋め例題→類題でステップを踏める
- 薄いので取り組みやすく達成感がある
の3つだと思います。
掘り下げて見ていきましょう。
苦手な計算をピンポイントで復習できる
計算分野を37テーマに分けてくれているので、苦手な計算をピンポイントで復習できます。
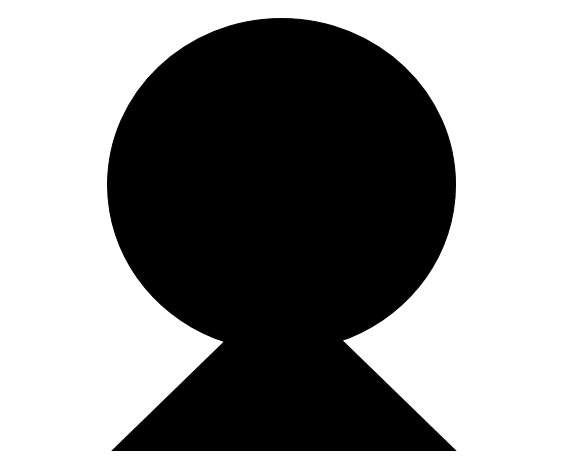
小数と分数が混ざると苦手…
逆算(□算)をいつもまちがえる…
苦手な計算って、人それぞれですよね。
苦手意識がある計算テーマを集中的にトレーニングすることができます。
中には「どこが苦手なのかもわからない…」という子もいるかもしれません。
その場合には、「マスター問題」(類題)や「たしかめテスト」(章末問題)をノーヒントで解いてみることで、苦手をあぶりだすこともできるでしょう。
例題→穴埋め例題→類題でステップを踏める
塾で配られる計算問題集では、例題がない問題集も多いです。
例題なしで、あえてランダムに並べることで、対応力を鍛えるためでしょう。
でも、計算の基礎があやふやな子には、ハードルが高い場合が多いでよね。
でも、「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」では、さきほど紹介した通り各テーマが
- よんでわかる【例題】
- かいてデキる【穴埋め例題】
- マスター問題【類題】
というスモールステップになっているので、ご家庭でも「例題→穴埋め例題→類題」の順番で学べます。
筋トレと同じで、トレーニングしている部位(テーマ)を意識しながら、練習できるでしょう。
薄いので取り組みやすく達成感がある
100ページ程度の薄めの問題集です。
1日1テーマずつ進めていけば、1か月くらいで1巡できます(全37テーマ)。
1テーマの類題も8問くらいなので、1日の負担も大きくありません。
得意な計算テーマについては、飛ばしてもいいでしょう。

問題集が分厚かったり、問題数が多いと、ちょっとしんどいやん
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」はどんな子におすすめ?
どんな子に向いているのかというと…
- 計算のつまずきが多い子
- 計算まちがいの原因がわからない子
- 塾で計算問題集が配られていない子
- 塾の計算問題集が難しすぎる子
の4タイプだと私は思います。
1つずつ見ていきましょう。
計算のつまずきが多い子
よく「計算ミス」という言い方をしますが、単なる「ミス」で片づけてしまうのは怖い…
ただただ計算方法が身についていない場合、それはミスではなく、実力不足・トレーニング不足と言えますね。
- 約分でまちがいが多い
- 小数→分数の書き換えでもたつく
- 逆算のひき算・わり算の正答率が低い
こういうことはよくあります。
計算方法が身について場合、いくら「ミスに気を付けよう」とか「見直しをしよう」と言っても、見直してもミスに気づけません。
まずは、苦手な計算テーマを集中的に克服したほうがいいでしょう。
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」は、計算テーマが細かく分かれているので、集中的な復習がしやすいです。
計算まちがいの原因がわからない子
中には漠然と「計算が合わない…」という子もいます。
つまり、どこで計算まちがいをしているのか、本人がよくわかっていません。
そういう場合には、「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」の、「マスター問題」(類題)や「たしかめテスト」(章末問題)をノーヒントで解いてみましょう。
苦手な計算テーマが、あぶりだされてくるはずです。

「何がわからないかが、わからない」ってヤツやな
苦手な計算テーマが見つかったら、1つずつ克服していきましょう。
塾で計算問題集が配られていない子
ほとんどの塾で、計算問題集や計算プリントを持たされます。
どの塾も、計算の大切さを理解しているからです。
でも、中には計算問題集を購入させていない塾もあります。
以前、個別指導塾に通っている子を担当したのですが、計算が苦手なのに、その個別指導塾では計算問題集や計算プリントを使っていませんでした。

中学受験が手薄な個別指導には注意しましょう
ご家庭に説明して、「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」を購入してもらいました。
2~3巡する頃には、計算が安定してきました。
文章題や図形の学習を進めながらも、計算力をつけるために、計算トレーニングを継続することは大切ですね。
塾の計算問題集が難しすぎる子
また、塾で使っている計算問題集・計算プリントが、難しくて「自分には合っていない…」という子もいるでしょう。
自分のレベルに合っていない問題を解いていても、効果は出にくいですよね…
まずは自分に合ったレベルの問題集で、苦手を克服していくことが大事です。
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」のような教材で、基礎固めをするといいでしょう。
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」の効果的な使い方は?
次に、効率的な使い方を見ておきましょう。
- 【苦手意識強め】「よんでわかる」から順番に
- 【弱点がわからない】例題や章末問題を解いてみる
- サイクル学習
- タイムプレッシャーをかける
の4タイプを紹介しておきます。
掘り下げて紹介していきますね。
【苦手意識強め】「よんでわかる」から順番に
まず、計算に苦手意識が強い場合には、「よんでわかる」【例題】からていねいに進めていくといいでしょう。
少しずつ苦手意識も取り去っていくことが必要になります。

え?!
こんな計算していたの?!
子どもって、おとながびっくりするような間違い・思い違いをしているものです。
「例題→穴埋め例題→類題」のステップを踏むことで、知識とテクニックを積み上げていくことができます。
そして、「できた!」という自信も積み上げていきましょう。
【弱点がわからない】例題や章末問題を解いてみる
「計算ミスの原因がわからない」といういう場合には、さきほども紹介した通り、苦手な計算テーマをあぶりだすことから始めてみましょう。
例題を隠して、ノーヒントで「マスター問題」(類題)や「たしかめテスト」(章末問題)を解いてみます。
すると、
- しっかりと正解できる計算
- よくまちがう計算・あやふやな計算
が見えてくるでしょう。
苦手な計算テーマがあぶりだされたら、「よんでわかる」(例題)や「かいてデキる」(穴埋め例題)も使って、克服していきましょう。
サイクル学習
どんな問題集も同じですが、1巡しただけでパーフェクトにマスターできるわけではありません。
2~3巡繰り返すことによって、だんだんと知識とテクニックが定着してきます。
もちろん得意な計算、すでにできている計算は、それほど繰り返す必要はありません。
苦手なテーマの問題を繰り返し解いて、すらすらと自力で解けるようにしましょう。

「サイクル学習」とか「スパイラル学習」とか言いますよね
新しい問題集で「おかわり」して、量をこなすことも大切ですが、まずは1冊をやりこみ、その1冊からしっかりと栄養分を吸収することも重要ですね。
タイムプレッシャーをかける
計算に時間がかかってしまう子には、意識的に焦ってもらいましょう。
「マスター問題」(類題)の8問を解くときに、制限時間を設けます。
いわゆる「タイムプレッシャー」をかけることで、スピードアップを目指します。
「計算の下地ができているけれども、スピードがゆっくり」という子に有効です。
一方、計算の基礎力がついていない場合には、まだタイムプレッシャーをかけない方がいいでしょう。
スピードよりも、まずは正確さが優先です!

スピーディーに間違っても意味ないな…
タイムプレッシャーは、もちろん他の教材でも使えるので、マイペースなお子さんにぜひ使ってあげてくださいね。
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」の注意点は?
では、使うときの注意点は何でしょうか。
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」を使うときの注意点は…
- おとなの付き添いが必要
- 1冊では練習量は足りない
- どちらかというと復習向き
- これでも難しい子には小学校ドリルから
の4点です。
掘り下げて見ておきましょう。
おとなの付き添いが必要
どの教科もそうですが、小学生は独学は難しいです。
ましてや苦手な教科・単元を、自分で問題集の解説を読んで勉強することはできません。
中には、自分を律して、自分で学べるスペシャルな子もいますが、なかなかそうはいかないのが現実です…
おとなが付き添って、
- 例題を説明してあげる
- 丸つけしてあげる
- まちがったポイントを見つけてあげる
必要があります。
お母様・お父様もお忙しいので、付き添ってあげられないことも多いでしょう。
その場合には、個別指導や家庭教師などの外部の手を借りるのがおすすめです。
ただし、中学受験の勉強は、大学生のアルバイト講師には荷が重いことがよくあります。

つるかめ算を連立方程式で教えちゃうとか…
ですので、料金は高くなりますが、プロ講師を利用したほうが、コスパが良いことはよくあります。
プロ講師につまずきポイントを見極めてもらい、適切な課題を出してもらい、トレーニングをした方が結果が出やすい場合も多いでしょう。
1冊では練習量は足りない
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」は、薄めのテキストで、見開きで類題が8問だけです。
もちろん2巡3巡繰り返して、1冊の問題集を仕上げることが先決です。
ただ、他の教科やどの問題集でも同じように、「おかわり」をして量をこなす必要があります。
この問題集から栄養分をじゅうぶんに摂取できたと感じたら、難しめの計算や総合問題にステップアップしていくといいでしょう。
どちらかというと復習向き
予習として使う場合にも、問題数が少な目なのがネックになります。
新しい計算を学ぶときには、どうしてもたくさん問題を解いて反復する必要があります。
頭で考える段階から、体が計算を覚えている段階に引き上げなければなりません。
ですので、「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」は、一度学んだ計算の復習に使った方がいいと私は思っています。
これでも難しい子には小学校ドリルから
「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」は、中学受験算数の計算の基本をまとめてくれています。
ですので、このテキストが難しく感じるなら、小学校の計算でつまずいている可能性が高いです。
その場合には、ムリせずに、まずは小学校の計算ドリルからしっかりとやり直したほうがいいでしょう。
まとめ:「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」をプロがレビュー
志望校に合格するには、塾のカリキュラムに乗り、教材を使うこなすことが近道です。
ただ、塾の教材のレベルが、自分に合っていない場合には、ご家庭でフォローしなければなりません。
そういう子には、私は「中学入試算数のつまずきを基礎からしっかり[計算]」を使って、指導しています。
皆さんの計算の苦手克服の参考になれば幸いです。



