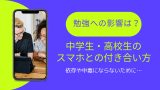こんにちは、プロ家庭教師のひかるです。

挫折してまう…
どうやって勉強を計画通りに進められるん?
そのように悩んでいる高校生も多いですよね。
小学生・中学生と違って、高校生は自分で勉強を管理できるように成熟しつつあります。
コツさえつかむことができれば、勉強を計画通りに進めやすくなるでしょう。
今回の記事では…
- 高校生の勉強計画の理想と現実
- 計画通りに勉強が進まない原因5つ
- 挫折しにくい計画を立てる5つのコツ
がわかります。
また、私が使っている2つの勉強計画表のテンプレートも、無料でダウンロードできます。
勉強計画をうまく活用して、大学受験や定期テストに挑んでくださいね!

元塾講師・現プロ家庭教師として、のべ1000人以上を担当してきたノウハウをお伝えします
高校生だからこそ勉強を自己管理できる!

このサイトでは、小・中学生についての記事は、保護者向けに書いています。
でも、この記事は、高校生のみなさんに向けて書いています。
なぜなら、高校生は自分で勉強を管理できるくらい成長してきているからです。
たとえば、「答えを見たり写したりしてはいけないよ!」と言っても、小学生・中学生はついつい答えを見たり写したりしてしまいます。
自分でも良くない、意味のないことだとわかっていながらも、誘惑に負けてしまいます。
また、お母さん・お父さんに丸つけしてもらったり、解き直しをする問題を指示してもらったりしなければならない子もいます。
まだまだお母さんやお父さんに勉強を「させられている」と感じている子も多いでしょう。

悪気はないねんけどな
一方、高校生はお母さんやお父さんの手を離れて、自分なりに勉強できるようになってきています。。
むしろ親に口出しされると、イヤですよね…
ただ、勉強を効率的に進める方法や、挫折しにくい方法がまだ身についていないという子も多いのも事実です。
勉強がうまくいく「仕組み」さえわかれば、勉強がはかどるでしょう。
この記事で紹介する勉強計画の作り方・コツで、ぜひ自分を律して勉強を継続していきましょう!
勉強計画表の作り方【理想バージョン】

まずは、一般的に言われている勉強計画表の作り方から紹介しておきます。
理想的だとされる勉強スケジュールの立て方は、
逆算式の勉強計画
です。
「逆算式」というのは、目標を決めて、その目標を達成するために必要なことを、期限から逆算してスケジュールに落とし込んでいく方法です。
たとえば、
大目標:志望校合格
↓
中目標:夏休み中に、日本史一問一答問題集を1冊(150ページ)終わらせる
↓
小目標:夏休みは日本史一問一答問題集を毎日5ページ(150ページ÷30日)進める
という感じです。
めっちゃ理想的ですね。

それくらい知ってるわ!
理想通りに行かへんから悩んでるんや!
というみなさんの声が聞こえてきそうです…
実際にはいろいろなことが、原因で計画通りには進まないものです。
※計画通りに進まない原因は、後で紹介していきます。
勉強計画表の作り方【現実バージョン】
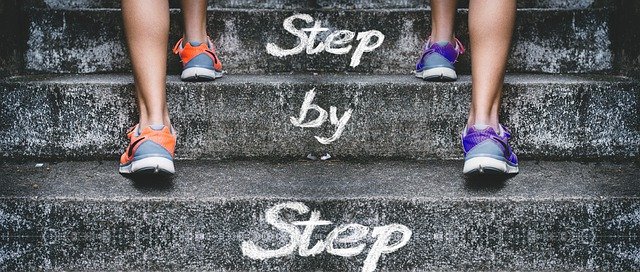
では、理想通りにいかないなら、どんな勉強計画を作ればいいのでしょうか?
現実的な勉強スケジュールの立て方は、
積み上げ式の勉強計画でスタートする
ことです。
「積み上げ式」というのは、1日にできることを先に把握して、仮のスケジュールを作っていく方法です。
たとえば、さきほどの150ページある日本史一問一答問題集を例にして考えてみましょう。
まずは、ひとまず試しに数ページ解いてみましょう。
とりあえず手をつけてみることで、
- 1ページにかかる時間
- 問題の難易度
などが把握できます。
すると、

1ページに15分かかったから、1時間で4ページくらい進むな
というようにペース配分がわかるようになります。
ペースがわかれば、計画表に勉強スケジュールを落とし込みやすくなりますね。
得意な単元はペースアップして、苦手な単元はペースダウンして、計画を立ててもいいでしょう。。
また、波に乗れば、「逆算式の勉強計画」に切り替えるのもおすすめです。
「積み上げ式」では、目標の期限までに間に合わない可能性があります。
ですので、「積み上げ式」で始めて、「逆算式」でペースを調整するのが現実的な勉強スケジュールだと言えます。
計画通りに勉強が進まない原因5つ

ここまでざっくりと、勉強計画の理想と現実を見てきましたが、計画の通りに勉強がはかどらない原因はいくつかあります。
その原因を自覚しておいた方が、計画通りに勉強が進めやすくなります。
計画通りに勉強を進められない原因は…
- 勉強する習慣ができていない
- 勉強する環境が整っていない
- ついついスマホを触ってしまう
- 勉強のやり方が決まっていない
- そもそも計画に無理がある
の主に5つです。
1つ1つ見ていきましょう。
勉強する習慣ができていない
ふだんから勉強する習慣ができていない場合、「今日から勉強するぞ!」と意気込んでもなかなか続きません。
というのも、別の習慣ができ上がってしまっているからです。
たとえば、
- 部活して家に帰る
- 晩ご飯を食べる
- テレビを見て家族と話す
- 風呂に入る
- スマホでゲーム・SNS
- 寝る
というような生活習慣がすでに完成している人も多いでしょう。
つまり、「勉強しない習慣」ができ上がっているわけです。
これではなかなか計画通りに勉強を進めにくい…
勉強する環境が整っていない
また、勉強する環境が整っていない場合も、勉強計画が挫折しやすいです。
たとえば、
- 勉強部屋に冷暖房がない
- 文房具がそろっていない
- 教材がそろっていない
- 机の上がマンガだらけ
- 常にスマホが目の前にある
などですね。
こういう状態では、勉強を始めようとしても、「暑すぎて無理!」、「あ、解答がないから勉強できない」、「SNSの通知きてる」…
その結果、「ついつい勉強をしなくてもいいか」と後回しになってしまいます。
つまり、「勉強をしない言い訳」をしやすい環境になっているでしょう。
ついついスマホを触ってしまう
誰もがスマホを持っている時代です。
日常生活もスマホがないと、生きていけません。
高校も予備校も教材も、スマホがあることを前提にして成り立っています。
連絡事項やテスト範囲、欠席したときの配信授業、英語の音声再生QRコード…なんでもオンラインでできてしまいます。

そこのあなた!
この記事もスマホで読んでいますね!
でも、スマホがあるせいで、勉強が進まないのも事実!
アンデシュ・ハンセンさんの『スマホ脳』という本には、次のようなデータが載っています。
英国ではロンドン、マンチェスター、バーミンガム、レスターにある複数の学校でスマホの使用を禁止した。生徒たちは朝スマホを預け、学校が終わると返してもらう。その結果、成績が上がった。
『スマホ脳』アンデシュ・ハンセン
スマホのせいで勉強がはかどらないのは、あなただけではありません。
日本だけでなく、世界的な問題なんです。
勉強のやり方が決まっていない
なんとか誘惑に打ち勝って、勉強をスタートしたとします。
でも、なかなか勉強がはかどらないことがあります。
それは、
- どの教材を
- どのように
- どこまで
勉強したらいいのかを決めていないときによく起こります。
なんとなく勉強を始めてしまうと、なんとなく勉強を辞めてしまうことにつながります。
また、「この方法で効果が出るのかな…」という疑心暗鬼の状態では、自信を持って勉強を進めにくいでしょう。
そもそも計画に無理がある
さきほど「逆算式の勉強計画」が理想だとお伝えしました。
ただ、期限から逆算して計画を立てると、ムリな計画を立ててしまいがちです。
150ページ÷30日=5ページ/日というただ逆算したでは、ギューギューにスケージュールを詰め込んでしまうことがあります。
計画にそもそも無理があると、計画通りに進まないのは当然ですよね。
一度計画通りに進まなくなると、ずるずると勉強しなくなってしまう人も多いでしょう。
その結果、「やってもダメだ…」、「自分が意志が弱い」というような無力感を感じてしまいます…
挫折しにくい勉強計画を作るコツ5つ

計画通りに勉強が進まない理由から、挫折しにくい勉強計画の作り方が見えてきます。
継続しやすい勉強スケージュールの立てるコツは、
- 勉強に使える時間を確保する
- 勉強できる環境を整える
- スマホなど誘惑を遠ざける
- 勉強のやり方を決める
- 積み上げ式の計画から始める
の5つです。
掘り下げて見ていきましょう。
勉強に使える時間を確保する
勉強する習慣がまだできていない場合には、まず「習慣づくり」をしましょう。
つまり、生活の一部に勉強を取り込むということです。
ご飯を食べる、風呂に入る、歯を磨くのと同じように「勉強する」を一日のスケジュールに固定します。
習慣化するコツは、勉強時間の「天引き」です。
「天引き」というのは、必要な分を先に確保しておくことです。
実業家の本田直之さんは、『レバレッジ勉強法』という本の中で、次のように書かれています。
100パーセントその通りにいかなくても、なんらかのベースがあったほうがラクですし、毎日何をやるか一から考えるのは大いなる無駄なのです。(中略)
『レバレッジ勉強法』より引用
貯金は「天引き」がいちばん良いとされるように、勉強時間も天引きし、あらかじめ強制的に確保することにしましょう。
後回しにしていると、勉強する時間はずるずるとなくなってしまいます。
勉強を日々のルーティンにすることで、スムーズに勉強をスタートできます。
また、習慣化には「3」という数字が重要だと言われています。
- 3日
- 3週間
- 3か月
まずは、3日続けましょう。
「三日坊主」という言葉がありますが、この3日で習慣化が失敗するわけですね。
3週間続けると、かなり負担なく日常に溶け込んでいるはず。
そして、3か月続けると、もう習慣化できていると言えるでしょう。
勉強できる環境を整える
勉強する環境がまだ整っていない場合には、勉強しやすい環境を見つけましょう。
さきほどの例であれば、
- 勉強部屋に冷暖房がない→冷暖房のある部屋で勉強する
- 文房具がそろっていない→そろえる
- 教材がそろっていない→そろえる
- 机の上がマンガだらけ→見えないところに片づける
- 常にスマホが目の前にある→通知が聞こえないように遠ざける
などですね。
もし家の中で勉強しにくい場合には、家の外で勉強するのもありです。
高校や図書館、塾・予備校の自習室などの方が、集中できる高校生は多いです。
高校生なので、ファーストフード店やカフェなどで、勉強してもいいですね。
周囲の目がある方が、「オレは勉強してるねんで!」という気持ちになれるものです。

友達といっしょに勉強するのは、あまりおすすめしません
スマホなど誘惑を遠ざける
環境を整える一環として、勉強の邪魔になるものは、できるだけ遠ざけてしまいましょう。
特にスマホとの距離感が難しい…
中にはスマホで英単語の意味などを調べながら勉強するという高校生も多いでしょう。
もちろん自分を律して、スマホを「勉強道具」として使えるのなら積極的に使っても大丈夫です。
でも、勉強以外に使ってしまっているなら、遠ざけた方が良いです。
さきほど紹介したアンデシュ・ハンセンさんの『スマホ脳』では、次のようなデータも載っています。
大学生500人の記憶力と集中力を調査すると、スマホを教室の外に置いた学生の方が、サイレントモードにしてポケットにしまった学生よりもよい結果が出た。(略)ポケットに入っているだけで集中力が阻害されるのだ。(中略)
ポケットの中のスマホが持つデジタルな魔力を、脳は無意識のレベルで感知し、「スマホを無視すること」に知能の処理能力を使ってしまうようだ。その結果、本来の集中力を発揮できなくなる。
『スマホ脳』より引用
つまり、スマホが近くにあるだけで、パフォーマンスが落ちるんです。
ついついスマホを触ってしまって勉強が進まないなら、スマホは別の部屋に置くなどして、手の届かないところに置いておくといいでしょう。
少なくとも、SNSの通知が鳴らないように設定して、スマホを使う時間を決めておいた方がいいかもしれません。

おとなでもスマホに依存してるけどな
依存度が強くて、自分ではなかなか手放せない場合には、家族の手も借りるといいでしょう。
※高校生のスマホとの距離の取り方については、こちらの記事もどうぞ↓
勉強のやり方を決める
勉強できる環境が整ったら、勉強のやり方を決めましょう。
具体的には、
- どの教材を
- どのように
- どこまで
勉強するのか決めます。
自分に合った教材で、効果の出る方法で勉強しなければ、力はつきません。
ポイントは「どのように」勉強するかです。
くれぐれも「形だけ」の勉強に陥らないようにしましょう。
私は形だけの勉強を「だけ勉」と呼んでいます。
- 教科書を見るだけ
- マーカーを引くだけ
- ノートに写すだけ
- 答えを写すだけ
- 提出するだけ
これらの方法は、頭をあまり使わない効果の薄い勉強法です。
逆に効果がある勉強法は、「自分で解けるトレーニング」です。
何も見ずにテスト本番で解けるためには、勉強の段階でも自力で解けなければなりません。
つまり、知識を頭から出すこと(=アウトプット)を意識して勉強することが大切です。
「どの教材をどのように勉強していいのかわからない…」という場合には、高校の先生や塾講師に相談してみましょう。
また、苦手意識が強い場合には、個別指導や家庭教師を利用するのも1つの手です。
積み上げ式の計画から始める
また「逆算式の勉強計画」でうまくいっていない場合には、「積み上げ式」の勉強計画に切り替えるといいでしょう。
計画通りに勉強が進むことはなかなかありません。
急な用事が入ることもありますし、体調を崩すこともありますし、やる気は出ない日もあります。
ですので、うまくいかなかったときに、どう修正するかが大切です。

三日坊主になっても、4日目に勉強を再開すれば大丈夫!
積み上げ型で計画表を作っておき、いったん走り出してみましょう。
勉強を始めてみたら、うまくいく部分とうまくいかない部分が見えてきます。
うまくいく部分を参考に、うまくいかない部分を修正していけばOKです!
そして、波に乗ったら「逆算式」の勉強スケジュールを考えて、目標・期限まで走りましょう。
【ダウンロード無料!】2つの勉強計画表テンプレート

どんな勉強計画表が自分に合うのかは、人それぞれです。
自分に合った勉強計画表を見つけていくのが1番です。
生徒手帳でも市販のスケジュール帳(月間・週間など)でもOKです。
私は「スタープランナー」という本型の手帳を使っています。
基本的には月間・週間のスケジュールなのですが、大谷翔平選手も目標を書いたというマンダラチャートや、習慣化して自信を高めるコツなどもまとめられています↓
また、私が作ったオリジナルの勉強計画表テンプレートも2つ紹介しておきます。
「どんなスケジュール帳を使えばいいのかわからない…」という人は、よければ使ってみてください!
- 1週間の勉強計画表
- 1か月の勉強計画表
の2タイプです。
無料でダウンロードできるので、印刷して使ってくれてOKです。
両方を使う必要はありません。
「こっちの方が使いやすそうだな」という方を、使ってみてくださいね。
1週間の勉強計画表
まず1つ目がスタンダードな1週間の勉強計画表です↓
1週間の時間の使い方が把握できるのがメリットです。
ふだんバージョンを作っておき、テスト前にはテスト対策バージョンを作ってもいいでしょう。
使い方はこんな感じです↓
- 学校・クラブ・塾・習い事・生活の時間を、先に書きだします。
- 勉強に使う時間を決めます。
- どの教科のどの単元を学習するのかを決めます。その際、「教材・どのように勉強するか」も決めておきます。
- 休憩時間も取ります。
- 計画がうまくいかなかった場合には修正して、次に活かします。
- 〇の欄:うまくいったこと、△の欄:次に活かすこと、など書きます。
- 自分だけでなく、家族も見られるよう、コピーしたり、リビングや冷蔵庫に貼ったりしておきましょう。
計画を立てるのに時間をかけすぎるよりも、仮で作ったら、いったん勉強を始めましょう。
そして、不具合が出てきたら、修正するというやり方でOKです。
このようにやるべきことを「見える化」することで、勉強に取り組みやすくなります。
1か月の勉強計画表
もう1つは、1か月の勉強計画表です。
計画表でありながら、進度チェックができるのがメリット↓
31日分のマスがあるので、勉強したいページ・問題番号・単語番号を、日付の上段に書き込みます。
下段には、勉強した日付を書いて、実行した手ごたえを感じましょう。
立てた予定よりも、早めに実行できると「計画通り以上にできている!」という自信になります。
週間の勉強計画と同じように、ゆとりのある計画からスタートして、修正を加えていくといいでしょう。
勉強計画に行き詰ったら人の手を借りる

ここまで勉強計画の作り方や、実際のテンプレートを紹介してきました。
でも、

自分では計画が立てられない…
計画を立てても、勉強できない…
という高校生も多いでしょう。
もちろん誰もがすぐに計画を立てて、その通りに実行できるわけではありません。
試行錯誤して、自分がやりやすい方法を少しずつ見つけていけば大丈夫です。
ただ、定期テストや大学受験というタイムリミットがあります。
中には進級がかかっている、留年が目前という人もいるかもしれません…
「自分だけではプランが作れない…プラン通りにいかない…」という人は、他の人の手を借りましょう。

計画を立てて実行し、成功させるのは、大人だって難しいですよ…
お母さん・お父さん、お姉さん・お兄さんなど、家族を頼れる場合には、家族にサポートしてもらうといいでしょう。
勉強計画表を家族にチェックしてもらうだけでも、「勉強しなきゃ!」というモチベーションになります。
家族だとケンカになる…という人は、高校の先生や塾講師に相談してみてもいいでしょう。
また、家庭教師や個別指導を利用するのも1つの手です。
家庭教師や個別指導なら、マンツーマンなので、勉強のペースメイクがしやすいです。
まとめ:高校生の勉強計画表の作り方【2つの無料テンプレート付き】
高校生は、自分で学習の管理ができるほど、習熟しつつあります。
自分の手帳や、私が紹介した勉強計画テンプレートを使って、勉強計画表を作ってみてくださいね。
そして、計画を立てることも大事ですが、実際に勉強することがもっと大切です。
計画を立てるだけでは、力はつきません!
計画を立てて実行するという力は、大学に入ってから、社会に出てからも、めっちゃ役に立ちます。
ぜひみなさんが勉強計画表を通じて、勉強だけでなく、自分を律する力を身につけられるよう応援しています!